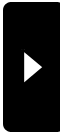弁護士と事務員の恋愛事情
2020年10月26日
法律事務所のメンバーと言えば、弁護士と事務員ですが、弁護士と事務員との間の交際・恋愛って多いものなんでしょうか?

筆者の所属する滋賀県のような、地方の法律事務所で言えば、弁護士と事務員との交際は、「ないわけじゃないけど、ほとんど見ない」というのが現状かなと思います。
地方の町弁(町医者的弁護士)の事務所の場合、多くても弁護士数名・事務員数名程度の規模のことがほとんどで、そのような零細企業内での社内恋愛って、万が一破局したときに双方が大きなダメージを負います。したがって、仮に交際していても、ゴールイン=結婚するまでは誰にも言わずに秘密裏に交際することが多く、筆者が知っているケースも、結婚したことを聞いて、「弁護士と事務員さんが付き合っていたんだ」と初めて知ったことがほとんどです。
他方、違う事務所の弁護士と事務員が付き合う機会はほとんどありません。弁護士と他の事務所の事務員が一緒にご飯を食べに行ったり、遊びに行ったり、連絡先を交換したりする機会がないんです。滋賀のような狭い世界だと、違う事務所の弁護士と事務員が合コンなんてすると、またたく間に噂が知れ回ってしまうので、そのような機会は皆無なんですよね。
というわけで、弁護士と事務員の恋愛って、実はほとんどないんですよね。
東京や大阪のように、事務所に弁護士や事務員が何百人もいるとか、そもそも県内に弁護士が何千人もいる状況ですと、もしかしたら滋賀とは違って弁護士と事務員の交際も結構多いのかもしれませんね

筆者の所属する滋賀県のような、地方の法律事務所で言えば、弁護士と事務員との交際は、「ないわけじゃないけど、ほとんど見ない」というのが現状かなと思います。
地方の町弁(町医者的弁護士)の事務所の場合、多くても弁護士数名・事務員数名程度の規模のことがほとんどで、そのような零細企業内での社内恋愛って、万が一破局したときに双方が大きなダメージを負います。したがって、仮に交際していても、ゴールイン=結婚するまでは誰にも言わずに秘密裏に交際することが多く、筆者が知っているケースも、結婚したことを聞いて、「弁護士と事務員さんが付き合っていたんだ」と初めて知ったことがほとんどです。
他方、違う事務所の弁護士と事務員が付き合う機会はほとんどありません。弁護士と他の事務所の事務員が一緒にご飯を食べに行ったり、遊びに行ったり、連絡先を交換したりする機会がないんです。滋賀のような狭い世界だと、違う事務所の弁護士と事務員が合コンなんてすると、またたく間に噂が知れ回ってしまうので、そのような機会は皆無なんですよね。
というわけで、弁護士と事務員の恋愛って、実はほとんどないんですよね。
東京や大阪のように、事務所に弁護士や事務員が何百人もいるとか、そもそも県内に弁護士が何千人もいる状況ですと、もしかしたら滋賀とは違って弁護士と事務員の交際も結構多いのかもしれませんね

民事裁判は原告VS被告ではない?
2020年10月19日
一般の方に、民事裁判のイメージを聞くと、おそらく原告と被告が激しくやりあうケンカを想像される方が多いのではないでしょうか?
でも実は、民事裁判って、原告VS被告で直接やり合う構図ではないって知っていますか?

民事裁判は、原則として書面で審理が進んでいきますが、提出する書面は全て「●●裁判所 御中」という形で、裁判所宛てになっています。相手にも副本が送られますが、あくまで裁判所に対して主張する、という形なんですよね。
つまり、上の図で言うと、民事裁判は原告VS被告という図①ではなく、原告と被告がそれぞれ裁判官に対して主張・説得して、判断権者である裁判官に有利な判決を出してもらう、という図②の構図なんです。
ですので、裁判期日の場面でも、原告の弁護士と被告の弁護士が直接言い争う・やりあうということはほとんどなくて、双方ともに裁判官に対して答える・話すという感じなんですよね。
ですので、裁判の書面の中で、相手をやっつけるために罵倒したり、相手の主張に(法的には無意味なのに)ムキになって反論したりする必要はないんです。裁判官にさえわかってもらえばそれでいいんですよね。
もしあなたが弁護士に裁判手続を依頼した際も、このイメージを忘れずにいた方が、弁護士との打ち合わせもスムーズにいくことが多いと思いますよ
でも実は、民事裁判って、原告VS被告で直接やり合う構図ではないって知っていますか?

民事裁判は、原則として書面で審理が進んでいきますが、提出する書面は全て「●●裁判所 御中」という形で、裁判所宛てになっています。相手にも副本が送られますが、あくまで裁判所に対して主張する、という形なんですよね。
つまり、上の図で言うと、民事裁判は原告VS被告という図①ではなく、原告と被告がそれぞれ裁判官に対して主張・説得して、判断権者である裁判官に有利な判決を出してもらう、という図②の構図なんです。
ですので、裁判期日の場面でも、原告の弁護士と被告の弁護士が直接言い争う・やりあうということはほとんどなくて、双方ともに裁判官に対して答える・話すという感じなんですよね。
ですので、裁判の書面の中で、相手をやっつけるために罵倒したり、相手の主張に(法的には無意味なのに)ムキになって反論したりする必要はないんです。裁判官にさえわかってもらえばそれでいいんですよね。
もしあなたが弁護士に裁判手続を依頼した際も、このイメージを忘れずにいた方が、弁護士との打ち合わせもスムーズにいくことが多いと思いますよ

タグ :民事裁判
「物」に関する裁判って難しい?
2020年10月16日
民事裁判の多くは、お金の請求か、不動産がらみの請求(登記手続など)です。
それに対して、「物」(動産)に関する裁判ってあまり多くないのですが、実は物に関する裁判は難しいことが多いって知っていますか?

物に関するトラブルというと、たとえば「同棲していた彼氏が出て行くときに、私の指輪を勝手に持って行ったので返して欲しい」とか、「知人に一時的に荷物を預けていたが、その中にあったはずのアルバムがなくなっている」などが例としてあげられます。
なぜこれらのトラブルを法的に解決することが難しいのでしょうか。
1.物が存在したことの証明が難しい
土地や建物などの不動産であれば、所有者等の動きは登記簿に記載されます。また、お金についても、銀行振込であれば、口座に履歴として残ります。
他方で、物の場合、元々あったのかどうかを立証することが難しいことが多いです。普段からそこにある物について、あることを立証するために写真を撮っている人は少ないでしょう。
相手が、「私は持って行っていない。最初からなかったのでは」などと反論したときに、元々相手が出ていく直前の時点でそこに指輪があったこと、そして相手が出ていくと同時になくなったこと、を証拠で立証するのは非常に難しいんです。
ちなみに、お金についても、振込ではなく現金で領収証等がなければ、やはり同じように立証が難しくなります。
2.物の特定が難しい
不動産の明渡しなどの場合、登記簿に載っている地番や地積などでどこのどの不動産かを特定できます。
また、金銭の請求の場合には、特に特定をしなくても、「いくら支払え」でOKです。
他方で、物の引渡しを求める場合、誰がみても他の物と混同することがないように、特定をする必要があります。たとえば指輪だと、メーカー名、材質、色味、石の種類、などになるでしょうか。
では、写真のアルバムだったらどう特定するのか、ペット(※法律上は物とされます)ならどう特定するのか、ぬいぐるみならどう特定するのか、などと考えると、非常に難しい問題になってきます。
3.物の価値の評価が難しい
不動産であれば、固定資産評価額や、不動産業者の査定額などで、おおよその価値がわかります。
他方で、写真のアルバムやぬいぐるみなどといった物だと、仮にそれらを相手方が誤って勝手に処分したとしても、いったいいくら請求できるのか、評価が難しいのです。
誤って勝手に処分した事例だと、損害賠償額は物の価値=評価額が限度となるのが通常です。でも、写真のアルバムや、使い古したぬいぐるみ(ただし、本人にとっては非常に大事な物)をいくらと評価するのかは非常に難しい上、おそらく評価額は非常に低くなってしまうのでしょうね。
というわけで、「物」に関する裁判はとっても難しいんです。
また、評価額が低い以上、弁護士としても弁護士費用が非常に安くなりがちで、正直あまり受けたくないという弁護士が多いのではないでしょうか
それに対して、「物」(動産)に関する裁判ってあまり多くないのですが、実は物に関する裁判は難しいことが多いって知っていますか?

物に関するトラブルというと、たとえば「同棲していた彼氏が出て行くときに、私の指輪を勝手に持って行ったので返して欲しい」とか、「知人に一時的に荷物を預けていたが、その中にあったはずのアルバムがなくなっている」などが例としてあげられます。
なぜこれらのトラブルを法的に解決することが難しいのでしょうか。
1.物が存在したことの証明が難しい
土地や建物などの不動産であれば、所有者等の動きは登記簿に記載されます。また、お金についても、銀行振込であれば、口座に履歴として残ります。
他方で、物の場合、元々あったのかどうかを立証することが難しいことが多いです。普段からそこにある物について、あることを立証するために写真を撮っている人は少ないでしょう。
相手が、「私は持って行っていない。最初からなかったのでは」などと反論したときに、元々相手が出ていく直前の時点でそこに指輪があったこと、そして相手が出ていくと同時になくなったこと、を証拠で立証するのは非常に難しいんです。
ちなみに、お金についても、振込ではなく現金で領収証等がなければ、やはり同じように立証が難しくなります。
2.物の特定が難しい
不動産の明渡しなどの場合、登記簿に載っている地番や地積などでどこのどの不動産かを特定できます。
また、金銭の請求の場合には、特に特定をしなくても、「いくら支払え」でOKです。
他方で、物の引渡しを求める場合、誰がみても他の物と混同することがないように、特定をする必要があります。たとえば指輪だと、メーカー名、材質、色味、石の種類、などになるでしょうか。
では、写真のアルバムだったらどう特定するのか、ペット(※法律上は物とされます)ならどう特定するのか、ぬいぐるみならどう特定するのか、などと考えると、非常に難しい問題になってきます。
3.物の価値の評価が難しい
不動産であれば、固定資産評価額や、不動産業者の査定額などで、おおよその価値がわかります。
他方で、写真のアルバムやぬいぐるみなどといった物だと、仮にそれらを相手方が誤って勝手に処分したとしても、いったいいくら請求できるのか、評価が難しいのです。
誤って勝手に処分した事例だと、損害賠償額は物の価値=評価額が限度となるのが通常です。でも、写真のアルバムや、使い古したぬいぐるみ(ただし、本人にとっては非常に大事な物)をいくらと評価するのかは非常に難しい上、おそらく評価額は非常に低くなってしまうのでしょうね。
というわけで、「物」に関する裁判はとっても難しいんです。
また、評価額が低い以上、弁護士としても弁護士費用が非常に安くなりがちで、正直あまり受けたくないという弁護士が多いのではないでしょうか

体温が高い人に対しても、旅館やホテルは宿泊拒否できない?
2020年10月12日
旅館やホテルにおいて、新型コロナウイルス対策として、チェックイン時に検温をし、37.5度以上であれば宿泊を控えてもらう、という対応をしている旅館・ホテルが増えてきていると思います。
しかしながら、実はこのような場合でも旅館やホテル側が宿泊拒否をすると「違法」になる可能性があるって知っていますか?

旅館業法という、昭和23年に制定された法律では、5条において宿泊拒否をしてはならないことが定められています。
第5条 営業者は、左の各号の一に該当する場合を除いては、宿泊を拒んではならない。
一 宿泊しようとする者が伝染性の疾病にかかつていると明らかに認められるとき。
二 宿泊しようとする者がとばく、その他の違法行為又は風紀を乱す行為をする虞があると認められるとき。
三 宿泊施設に余裕がないときその他都道府県が条例で定める事由があるとき。
伝染病にかかっている疑いがあるだけでは宿泊拒否できず、「明らかに認められるとき」でなければダメなんですよね。
そして、この規定は強行法規であると考えられているため、当事者間の契約や事前の告知で除外はできないと考えられています。
つまり、予約申込時に、「うちの旅館はチェックイン時に体温が高い方は宿泊できません」と明記していたとしても、そもそもそのような明記自体が旅館業法5条に違反すると考えられるのです。
したがって、この旅館業法の規定に従えば、ホテルや旅館としては、体温が高い人についてあくまで宿泊を控えて頂くよう「お願い」することしかできず、それでも泊めろという人に宿泊拒否をすることは現状ではなかなか難しいということになります。
ただ、この旅館業法の規定は、これまでも何度も改正・撤廃すべきという声があがっています。
宿泊客のニーズも多様化し、それに応える宿泊施設も多様化しています。「うちは●●の顧客のみ受け付けますよ」というような、特定の客層のみを受け付ける宿泊施設があってもよいように思われます。
旅館業法の規定は、この法律が制定された戦後の頃は、宿泊施設は社会的・公共的施設という側面が強く、また、人を選別して宿泊拒否が行われると、差別につながるから、ということも制定の理由にあったのかもしれません。しかし、宿泊施設が増え、ネットで簡単に予約ができる現在において、果たしてこの規定のままでよいのかは疑問が残ります。
なお、現状の規定でも、たとえば非常に高熱があるとか、新型コロナが非常に蔓延している地域で新型コロナ特有の症状が出ているとかであれば、「伝染性の疾病にかかっていると明らかに認められる」という範疇に入る可能性もありうるかもしれません。
また、宿泊拒否ができないからといって、「ちょっとくらい熱があっても泊まっていいや」などという考えで行動することは、たとえ法律違反ではないにせよ、社会的・道義的には好ましくないでしょう。
ホテル・旅館からの相談を受ける弁護士の立場からすれば、新型コロナの問題を機に、旅館業法(5条)の改正に向けて動きがあればいいなと思っています。
しかしながら、実はこのような場合でも旅館やホテル側が宿泊拒否をすると「違法」になる可能性があるって知っていますか?

旅館業法という、昭和23年に制定された法律では、5条において宿泊拒否をしてはならないことが定められています。
第5条 営業者は、左の各号の一に該当する場合を除いては、宿泊を拒んではならない。
一 宿泊しようとする者が伝染性の疾病にかかつていると明らかに認められるとき。
二 宿泊しようとする者がとばく、その他の違法行為又は風紀を乱す行為をする虞があると認められるとき。
三 宿泊施設に余裕がないときその他都道府県が条例で定める事由があるとき。
伝染病にかかっている疑いがあるだけでは宿泊拒否できず、「明らかに認められるとき」でなければダメなんですよね。
そして、この規定は強行法規であると考えられているため、当事者間の契約や事前の告知で除外はできないと考えられています。
つまり、予約申込時に、「うちの旅館はチェックイン時に体温が高い方は宿泊できません」と明記していたとしても、そもそもそのような明記自体が旅館業法5条に違反すると考えられるのです。
したがって、この旅館業法の規定に従えば、ホテルや旅館としては、体温が高い人についてあくまで宿泊を控えて頂くよう「お願い」することしかできず、それでも泊めろという人に宿泊拒否をすることは現状ではなかなか難しいということになります。
ただ、この旅館業法の規定は、これまでも何度も改正・撤廃すべきという声があがっています。
宿泊客のニーズも多様化し、それに応える宿泊施設も多様化しています。「うちは●●の顧客のみ受け付けますよ」というような、特定の客層のみを受け付ける宿泊施設があってもよいように思われます。
旅館業法の規定は、この法律が制定された戦後の頃は、宿泊施設は社会的・公共的施設という側面が強く、また、人を選別して宿泊拒否が行われると、差別につながるから、ということも制定の理由にあったのかもしれません。しかし、宿泊施設が増え、ネットで簡単に予約ができる現在において、果たしてこの規定のままでよいのかは疑問が残ります。
なお、現状の規定でも、たとえば非常に高熱があるとか、新型コロナが非常に蔓延している地域で新型コロナ特有の症状が出ているとかであれば、「伝染性の疾病にかかっていると明らかに認められる」という範疇に入る可能性もありうるかもしれません。
また、宿泊拒否ができないからといって、「ちょっとくらい熱があっても泊まっていいや」などという考えで行動することは、たとえ法律違反ではないにせよ、社会的・道義的には好ましくないでしょう。
ホテル・旅館からの相談を受ける弁護士の立場からすれば、新型コロナの問題を機に、旅館業法(5条)の改正に向けて動きがあればいいなと思っています。
相手方に弁護士がつく方が助かる?
2020年10月05日
弁護士が相手本人と交渉をしていると、たまに、「なんなら、こっちも弁護士つけるぞ!」とか、「俺だって弁護士に知り合いがいるんだぞ!」と言われることがあります。
おそらく、相手は張り合うつもりで言ってきているのだと思うのですが、実は、弁護士からすれば、むしろ『どうぞ是非弁護士をつけてくれ』と思うことが多いって知っていますか?

1 争点の本題のみに集中できる
双方に弁護士がついた場合、法律的な争点については激しく主張し合いますが、争点とは無関係な部分については、嫌がらせをするのではなく、きちんとした対応をすることが多いです。
たとえば、離婚事件の場合、年末が近くなると、年末調整に向けて、勤務先から被扶養者の扶養資格の確認書類(妻の所得証明書など)の提出を求められることがあります。夫側の弁護士が、妻側の弁護士に、所得証明書の提出を求めれば、妻側の弁護士もなぜ必要なのか理解しているため、依頼者(妻)に説明の上、夫側の弁護士に提出してくれることがほとんどです。
他方で、妻に弁護士がついていないようなケースの場合、「なぜ敵(夫)の弁護士にそんなのを渡さなくてはならないんだ」などと怒って、無視されてしまうことなどもよくあります。
また、離婚後には、被扶養者の健康保険証を返してもらう必要があるのですが、弁護士がついていないと元妻側がなかなか返してこないケースもあります。
2 着地点が見えてくる
特に離婚事件や相続事件の場合、弁護士から見ればある程度の解決点・着地点が見通せることがよくあります。そうすると、交渉の中でも、「わかりました、この点ではこちらが譲歩しますから、その代わりこの点はそちらが譲歩してもらえますか?」というような交渉が可能になることがあります。
他方で、相手に弁護士がつかずに本人の場合、共通の解決点が見通せるわけではないため、上記のような形での交渉がなかなか難しいことが多いです。
3 相手が弁護士に相談することにより、自分の主張が通らないことを理解する
「なんならこっちも弁護士をつけるぞ!」などとマウントを張ってくる当事者は、実は法律的に通らないこと・過剰なことを主張してくる人が多かったりします。
そんなときに、本当にその人が弁護士のところへ相談に行けば、「法律的にその主張は通らないよ」とアドバイスを受けて、あきらめる可能性が高くなるんですよね。
上記のような理由で、「こっちも弁護士をつけるぞ!」と言われると、むしろ「そうしてくれ」と心の中で思うケースは少なくありませんし、「弁護士をつけるかどうかはそちらの判断次第ですし、相談に行かれるのであればどうぞ行って頂ければと思います」と答えることもあります。
とは言っても、相手の弁護士に対してこういう発言をしている人は、なかなか弁護士に相談したり依頼したりしないことが多いんですけどね
おそらく、相手は張り合うつもりで言ってきているのだと思うのですが、実は、弁護士からすれば、むしろ『どうぞ是非弁護士をつけてくれ』と思うことが多いって知っていますか?

1 争点の本題のみに集中できる
双方に弁護士がついた場合、法律的な争点については激しく主張し合いますが、争点とは無関係な部分については、嫌がらせをするのではなく、きちんとした対応をすることが多いです。
たとえば、離婚事件の場合、年末が近くなると、年末調整に向けて、勤務先から被扶養者の扶養資格の確認書類(妻の所得証明書など)の提出を求められることがあります。夫側の弁護士が、妻側の弁護士に、所得証明書の提出を求めれば、妻側の弁護士もなぜ必要なのか理解しているため、依頼者(妻)に説明の上、夫側の弁護士に提出してくれることがほとんどです。
他方で、妻に弁護士がついていないようなケースの場合、「なぜ敵(夫)の弁護士にそんなのを渡さなくてはならないんだ」などと怒って、無視されてしまうことなどもよくあります。
また、離婚後には、被扶養者の健康保険証を返してもらう必要があるのですが、弁護士がついていないと元妻側がなかなか返してこないケースもあります。
2 着地点が見えてくる
特に離婚事件や相続事件の場合、弁護士から見ればある程度の解決点・着地点が見通せることがよくあります。そうすると、交渉の中でも、「わかりました、この点ではこちらが譲歩しますから、その代わりこの点はそちらが譲歩してもらえますか?」というような交渉が可能になることがあります。
他方で、相手に弁護士がつかずに本人の場合、共通の解決点が見通せるわけではないため、上記のような形での交渉がなかなか難しいことが多いです。
3 相手が弁護士に相談することにより、自分の主張が通らないことを理解する
「なんならこっちも弁護士をつけるぞ!」などとマウントを張ってくる当事者は、実は法律的に通らないこと・過剰なことを主張してくる人が多かったりします。
そんなときに、本当にその人が弁護士のところへ相談に行けば、「法律的にその主張は通らないよ」とアドバイスを受けて、あきらめる可能性が高くなるんですよね。
上記のような理由で、「こっちも弁護士をつけるぞ!」と言われると、むしろ「そうしてくれ」と心の中で思うケースは少なくありませんし、「弁護士をつけるかどうかはそちらの判断次第ですし、相談に行かれるのであればどうぞ行って頂ければと思います」と答えることもあります。
とは言っても、相手の弁護士に対してこういう発言をしている人は、なかなか弁護士に相談したり依頼したりしないことが多いんですけどね

タグ :弁護士