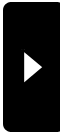弁護士はモテるの?
2009年04月30日
弁護士でない友人らと飲んでいると,「弁護士だったらモテるでしょ!?」などと言われることがよくあります。
実際のところ,弁護士ってモテるのでしょうか?
筆者の周りをみていると,弁護士は,結婚が早い人と遅い人に二極化する傾向があるように感じます。
弁護士って,いったんなってしまうと,意外と異性との出会いは多くありません。依頼者や事務員とそのような関係になってしまうと問題になりえますし,仕事も忙しいので,合コンに行く暇もあまりなかったりします。そうすると,弁護士になる前からお付き合いしている人と結婚すれば別ですが,そうでなければ,結婚が遅くなってしまうんでしょうね。
他方で,弁護士になる前からお付き合いしている人がいる場合,弁護士業が忙しくなると,新婚旅行とかで長期に休むことが難しくなりますし,披露宴で誰を呼ぶか迷うことになるので,弁護士になって早い段階で結婚をする人が多いようです。
というわけえ,『弁護士だからモテる』と感じることは,あんまりないんですよね
実際のところ,弁護士ってモテるのでしょうか?
筆者の周りをみていると,弁護士は,結婚が早い人と遅い人に二極化する傾向があるように感じます。
弁護士って,いったんなってしまうと,意外と異性との出会いは多くありません。依頼者や事務員とそのような関係になってしまうと問題になりえますし,仕事も忙しいので,合コンに行く暇もあまりなかったりします。そうすると,弁護士になる前からお付き合いしている人と結婚すれば別ですが,そうでなければ,結婚が遅くなってしまうんでしょうね。
他方で,弁護士になる前からお付き合いしている人がいる場合,弁護士業が忙しくなると,新婚旅行とかで長期に休むことが難しくなりますし,披露宴で誰を呼ぶか迷うことになるので,弁護士になって早い段階で結婚をする人が多いようです。
というわけえ,『弁護士だからモテる』と感じることは,あんまりないんですよね

タグ :弁護士
弁護士は六法は全て頭に入っているの?
2009年04月29日
自分が弁護士であるということを話すと,たまに,「じゃあ,六法は全て頭の中に入っているの?」なんて聞かれることがあります。果たして,弁護士は,六法はほとんど記憶しているのでしょうか?
実は,弁護士はそれほど条文自体を覚えいているわけではありません。また,弁護士・裁判官・検察官になるための最終試験(いわゆる二回試験)においても,六法は貸与され,参照することができます。条文自体は,六法を持ち歩いていつでも確認すればよいのであって,重要なのは,どの法律でどのような効果や手段がのっているのかということや,条文をどのように解釈するかということを知識として習得しているか否かなんですよね。
だからこそ,法律相談の場においては,六法全書(実際によく使うのは「模範六法」)が手放せないんですよね
実は,弁護士はそれほど条文自体を覚えいているわけではありません。また,弁護士・裁判官・検察官になるための最終試験(いわゆる二回試験)においても,六法は貸与され,参照することができます。条文自体は,六法を持ち歩いていつでも確認すればよいのであって,重要なのは,どの法律でどのような効果や手段がのっているのかということや,条文をどのように解釈するかということを知識として習得しているか否かなんですよね。
だからこそ,法律相談の場においては,六法全書(実際によく使うのは「模範六法」)が手放せないんですよね

タグ :弁護士
裁判はなぜ時間がかかるのか?
2009年04月28日
民事や家事の裁判って,判決に至るまで,半年や1年があっという間にたってしまいます。依頼者の方々からすれば,「もっと早く解決しないのか?」と疑問をもたれることでしょう。
では,なぜ裁判はこんなに時間がかかるのでしょうか?
民事や家事の裁判では,通常,1か月に1回程度のペースで裁判期日が開かれます。期日と期日の間に,当事者(弁護士)が書面で主張を提出し,期日の際に裁判官から今後の進行などについて指示がなされます。裁判になって,新たな主張なども出てくることがあるので,クライマックスともいえる証人尋問にたどり着くには,5~6回くらい期日を開かなくてはならないことが多く,それだけで半年近くたってしまうわけです。
この,裁判期日を,もっと頻繁に開けばいいわけですが,裁判所も混んでいますし,弁護士としても,たとえば1週間後に期日となると,弁護士はそれまでに依頼者と打ち合わせをして書面を作らなければならず,依頼者と時間の都合が合わなければ書面が作れなくなってしまいます。弁護士も裁判官も,数十件から100件以上の事件を同時並行で進めているので,結局は1か月に1回くらいの期日のペースでないと,回らないということになってしまうんですよね。
でも,新たに導入される裁判員制度では,裁判員の皆さんの負担も考え,裁判期日が連日開かれることになるそうです。その間は,弁護士も他の依頼者の事件をほったらかしにしなければならないわけで,かなり大変なことになりそうですね
では,なぜ裁判はこんなに時間がかかるのでしょうか?
民事や家事の裁判では,通常,1か月に1回程度のペースで裁判期日が開かれます。期日と期日の間に,当事者(弁護士)が書面で主張を提出し,期日の際に裁判官から今後の進行などについて指示がなされます。裁判になって,新たな主張なども出てくることがあるので,クライマックスともいえる証人尋問にたどり着くには,5~6回くらい期日を開かなくてはならないことが多く,それだけで半年近くたってしまうわけです。
この,裁判期日を,もっと頻繁に開けばいいわけですが,裁判所も混んでいますし,弁護士としても,たとえば1週間後に期日となると,弁護士はそれまでに依頼者と打ち合わせをして書面を作らなければならず,依頼者と時間の都合が合わなければ書面が作れなくなってしまいます。弁護士も裁判官も,数十件から100件以上の事件を同時並行で進めているので,結局は1か月に1回くらいの期日のペースでないと,回らないということになってしまうんですよね。
でも,新たに導入される裁判員制度では,裁判員の皆さんの負担も考え,裁判期日が連日開かれることになるそうです。その間は,弁護士も他の依頼者の事件をほったらかしにしなければならないわけで,かなり大変なことになりそうですね

タグ :裁判
弁護士と記録の保管
2009年04月27日
多くの弁護士が,「記録をどこにどのように保管するか」を悩んでいるって知ってますか?
裁判の事件記録って,膨大な量なんです。民事事件で争いとなって証人尋問までする事件であれば,少なくともタウンページ1冊分くらいの量になることが多いですし,争点が多い民事事件や,重大な刑事事件になると,タウンページ10冊分くらいの記録・資料になることも珍しくありません。事件が終わっても,すぐに廃棄するわけにはいかず,その保管場所の確保が結構大変なのです。
記録を全てスキャンして,電子データで保存してもよさそうですが,原本を残しておくべき資料があったり,紙媒体の方が一覧性に優れている面もあるので,完全に電子データだけにしている弁護士はあまりいません。そもそも,裁判所自体が,訴状や証拠書類を電子データではなく紙媒体で要求するので,どうしても弁護士の記録も紙媒体中心になってしまうんですよね。
筆者の事務所はとても狭いので,今後もどのように記録を保管していくか,考えていかなくてはなりません
裁判の事件記録って,膨大な量なんです。民事事件で争いとなって証人尋問までする事件であれば,少なくともタウンページ1冊分くらいの量になることが多いですし,争点が多い民事事件や,重大な刑事事件になると,タウンページ10冊分くらいの記録・資料になることも珍しくありません。事件が終わっても,すぐに廃棄するわけにはいかず,その保管場所の確保が結構大変なのです。
記録を全てスキャンして,電子データで保存してもよさそうですが,原本を残しておくべき資料があったり,紙媒体の方が一覧性に優れている面もあるので,完全に電子データだけにしている弁護士はあまりいません。そもそも,裁判所自体が,訴状や証拠書類を電子データではなく紙媒体で要求するので,どうしても弁護士の記録も紙媒体中心になってしまうんですよね。
筆者の事務所はとても狭いので,今後もどのように記録を保管していくか,考えていかなくてはなりません

弁護士には身分証明がない?
2009年04月26日
皆さんが,ある会社の社員であることを証明するためには,社員証などを見せたり,会社の健康保険証を見せたりすることが多いと思います。では,弁護士は,どうやって弁護士であることを証明するのでしょうか?
弁護士が弁護士であることを証明する代表的なものは,弁護士バッジです。ただ,一般の人の場合,そもそも弁護士バッジを見る機会自体が少ないので,本物のバッジかどうか見分けがつかないと思います。
でも,実は弁護士には,全員が携帯しているような身分証明書というのはありません。一応,弁護士会に申請すれば,有料で身分証明書を作ってはもらえるのですが,筆者の周りの滋賀の弁護士を見てみると,持っていない人の方が多いように思われます。また,弁護士会に申請すれば,たぶん弁護士であることの証明書みたいなものをA4の紙でもらえるとは思いますが,常時携帯できるようなものではありません。
結局,弁護士であることを証明するには,弁護士バッジに頼ることになるんですよね。ちなみに,弁護士バッジの裏には,弁護士固有の登録番号が刻まれており,これと日弁連のホームページで確認できる登録番号を照合すれば,偽物か本物か確かめることができます。
まあ,初めてあった弁護士に対して,「バッジの裏を見せて」なんてなかなかいえませんよね・・・
弁護士が弁護士であることを証明する代表的なものは,弁護士バッジです。ただ,一般の人の場合,そもそも弁護士バッジを見る機会自体が少ないので,本物のバッジかどうか見分けがつかないと思います。
でも,実は弁護士には,全員が携帯しているような身分証明書というのはありません。一応,弁護士会に申請すれば,有料で身分証明書を作ってはもらえるのですが,筆者の周りの滋賀の弁護士を見てみると,持っていない人の方が多いように思われます。また,弁護士会に申請すれば,たぶん弁護士であることの証明書みたいなものをA4の紙でもらえるとは思いますが,常時携帯できるようなものではありません。
結局,弁護士であることを証明するには,弁護士バッジに頼ることになるんですよね。ちなみに,弁護士バッジの裏には,弁護士固有の登録番号が刻まれており,これと日弁連のホームページで確認できる登録番号を照合すれば,偽物か本物か確かめることができます。
まあ,初めてあった弁護士に対して,「バッジの裏を見せて」なんてなかなかいえませんよね・・・