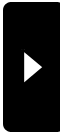戦前の法律もまだ生きている?
2024年11月18日
法律って、改定や廃止がなされなければ、かなり前に制定された法律でも効力は生きています。
実は我々の日常生活に関わる可能性がある有効な法律でも、戦前や、場合によっては100年以上前に作られたものもあるって知っていますか?

今日はそのような比較的身近なのに古い法律として、「失火責任法」と「盗犯等の防止に関する法律」をご紹介しましょう。
失火責任法とは、明治32年、つまり今から125年前に施行された法律で、正式名称は「失火ノ責任ニ関スル法律」と言います。
今でも健在で、しっかりと効力が生じています。
わずか1条しかない法律で、民法の不法行為責任について、失火の場合には故意・重過失の場合にしか適用しないとされています。
これは、明治時代などは現在よりも火事が起こりやすい上、一度起こると延焼の可能性が高く、全ての延焼被害者に対して失火した人が弁償するとなると莫大な額になってしまうため、その救済として制定された法律なのだと思われます。
次に、「盗犯等ノ防止ニ関スル法律」は、昭和5年に公布された法律ですので、既に94年前のものということになります。
簡単に言えば、家に入ってきた窃盗犯人が現金を盗み出そうとしているとか、凶器を持っているなどの場合には、その現場においては正当防衛の要件を緩和しますよ、というものです。
実際に窃盗などが行われている現場においては、被害者としてもカッとなったり、冷静に判断ができないことが多いと思われ、その場合の正当防衛を成立しやすくしているということなんですよね。
上記のような法律は、既に100年くらい前に制定されたものであっても、現在でも適用される身近な法律なんですよね。
日本には現在有効な法律は約2000弱くらいあるようです。
たとえ弁護士でも、知っている法律はそのうちのごくわずかなんですけどね
【滋賀県草津市の弁護士への相談はこちら】

滋賀の弁護士/草津駅前法律事務所
…このブログの筆者の事務所のメインサイト。

滋賀の弁護士による離婚相談
…離婚に関する相談サイト。

滋賀の弁護士の交通事故無料相談
…交通事故相談サイト。
実は我々の日常生活に関わる可能性がある有効な法律でも、戦前や、場合によっては100年以上前に作られたものもあるって知っていますか?

今日はそのような比較的身近なのに古い法律として、「失火責任法」と「盗犯等の防止に関する法律」をご紹介しましょう。
失火責任法とは、明治32年、つまり今から125年前に施行された法律で、正式名称は「失火ノ責任ニ関スル法律」と言います。
今でも健在で、しっかりと効力が生じています。
わずか1条しかない法律で、民法の不法行為責任について、失火の場合には故意・重過失の場合にしか適用しないとされています。
これは、明治時代などは現在よりも火事が起こりやすい上、一度起こると延焼の可能性が高く、全ての延焼被害者に対して失火した人が弁償するとなると莫大な額になってしまうため、その救済として制定された法律なのだと思われます。
次に、「盗犯等ノ防止ニ関スル法律」は、昭和5年に公布された法律ですので、既に94年前のものということになります。
簡単に言えば、家に入ってきた窃盗犯人が現金を盗み出そうとしているとか、凶器を持っているなどの場合には、その現場においては正当防衛の要件を緩和しますよ、というものです。
実際に窃盗などが行われている現場においては、被害者としてもカッとなったり、冷静に判断ができないことが多いと思われ、その場合の正当防衛を成立しやすくしているということなんですよね。
上記のような法律は、既に100年くらい前に制定されたものであっても、現在でも適用される身近な法律なんですよね。
日本には現在有効な法律は約2000弱くらいあるようです。
たとえ弁護士でも、知っている法律はそのうちのごくわずかなんですけどね

【滋賀県草津市の弁護士への相談はこちら】

滋賀の弁護士/草津駅前法律事務所
…このブログの筆者の事務所のメインサイト。

滋賀の弁護士による離婚相談
…離婚に関する相談サイト。

滋賀の弁護士の交通事故無料相談
…交通事故相談サイト。
どうやってネットから正しい法律知識を探せばよいか
2024年02月08日
みなさんは何か自分自身が法律問題に直面したとき、どうやって解決しようと思いますか?
いきなり弁護士に相談しようという人は少なく、おそらくまずはネットでググる(検索する)人が多いのではないでしょうか。
ただ、ネット上には不正確な法律知識もあふれています。では、どうやって正確な情報かどうかを見分ければよいのでしょうか?

①判例を引用しているかどうか
一番信頼できるかどうかのポイントは、法律のアドバイスや答えの後に、判例を引用しているかどうかです。判例を引用している場合、たとえば、
「・・・という事案の場合には、○○○であるとされています(最判平成●年●月●日)」
というような記載がなされます。
このような記載がなされている場合、執筆者は単に自分の考えを述べているのではなく、実際に判例の判示内容を踏まえているので、信用性が高いです。
もっとも、実際にその判例が自分自身の事例と一致しているのかどうかは要注意です。気になる場合には、裁判所のサイト内の裁判例情報から、実際にその事件の判決文を見ると、事例の詳細がわかることが多いです。
②執筆者が弁護士かどうか
弁護士は裁判のプロです。弁護士が、弁護士であることを明示して法律知識を記載している場合、信用性が高いことが多いです。
仮に宣伝目的のサイトであっても、弁護士である以上、誤った法律知識を掲載すると評判が下がったり場合によっては懲戒請求のリスクすら生じますから、正確な内容を記載している可能性が高いです。
他方で、弁護士ではないライターや、裁判を扱えない他の専門士業が記載した記事の場合、信用性が相対的に低くなりがちです。
ただし、法律や裁判例は時間とともに変わります。その記事を執筆したのがいつの時点なのかは確認する必要があります。
③理由付けや場合分けまでしっかりと記載されているか
法律問題って、数学のように「AならばB」と答えが1つになるとは限りません。というか、同じに見える事案でも、条件がつくと答えが全く変わってきます。
たとえば、
「配偶者が不貞行為をした場合、不貞相手に対して慰謝料請求ができます」
と書かれてあると、当然のように思えるかもしれません。
しかし、
①不貞行為前から婚姻関係が破綻していた場合にはできない。
②配偶者が既婚者であることを不貞相手が知らなかった場合にはできない。
③不貞行為と加害者を知ってから3年が経つとできない。
など、様々な事情によって答えは変わってきます。
さらに正確に言うと、
①の場合でも、婚姻関係破綻のハードルは高く、既に離婚協議をしていたとか、離婚前提で別居していた場合で無ければ、婚姻関係破綻と認定される可能性は低い。
②の場合でも、既婚者であると知らなかったことについて過失があれば、慰謝料請求できる。
など、さらに条件が加わると答えが変わってきます。
つまり、正確に法律知識を書こうとすると、どうしてもややこしい、まどろっこしい、長文になってしまうんです。
ネットでググっていると、どうしてもパッと答えを明快に書いている記事に目が移りますが、法律知識の場合むしろ長文で色々と場合分けしたり理由付けして書いている記事の方が、信用できる場合が多いんですよね。
といいながら筆者のこの記事も、グダグダと長文になってしまいました。
長文なので信用できると思ってくださいね(笑)
【滋賀県草津市の弁護士への相談はこちら】

滋賀の弁護士/草津駅前法律事務所
…このブログの筆者の事務所のメインサイト。

滋賀の弁護士による離婚相談
…離婚に関する相談サイト。

滋賀の弁護士の交通事故無料相談
…交通事故相談サイト。

個人事業・会社の破産・倒産無料相談
…会社の破産相談サイト。
いきなり弁護士に相談しようという人は少なく、おそらくまずはネットでググる(検索する)人が多いのではないでしょうか。
ただ、ネット上には不正確な法律知識もあふれています。では、どうやって正確な情報かどうかを見分ければよいのでしょうか?

①判例を引用しているかどうか
一番信頼できるかどうかのポイントは、法律のアドバイスや答えの後に、判例を引用しているかどうかです。判例を引用している場合、たとえば、
「・・・という事案の場合には、○○○であるとされています(最判平成●年●月●日)」
というような記載がなされます。
このような記載がなされている場合、執筆者は単に自分の考えを述べているのではなく、実際に判例の判示内容を踏まえているので、信用性が高いです。
もっとも、実際にその判例が自分自身の事例と一致しているのかどうかは要注意です。気になる場合には、裁判所のサイト内の裁判例情報から、実際にその事件の判決文を見ると、事例の詳細がわかることが多いです。
②執筆者が弁護士かどうか
弁護士は裁判のプロです。弁護士が、弁護士であることを明示して法律知識を記載している場合、信用性が高いことが多いです。
仮に宣伝目的のサイトであっても、弁護士である以上、誤った法律知識を掲載すると評判が下がったり場合によっては懲戒請求のリスクすら生じますから、正確な内容を記載している可能性が高いです。
他方で、弁護士ではないライターや、裁判を扱えない他の専門士業が記載した記事の場合、信用性が相対的に低くなりがちです。
ただし、法律や裁判例は時間とともに変わります。その記事を執筆したのがいつの時点なのかは確認する必要があります。
③理由付けや場合分けまでしっかりと記載されているか
法律問題って、数学のように「AならばB」と答えが1つになるとは限りません。というか、同じに見える事案でも、条件がつくと答えが全く変わってきます。
たとえば、
「配偶者が不貞行為をした場合、不貞相手に対して慰謝料請求ができます」
と書かれてあると、当然のように思えるかもしれません。
しかし、
①不貞行為前から婚姻関係が破綻していた場合にはできない。
②配偶者が既婚者であることを不貞相手が知らなかった場合にはできない。
③不貞行為と加害者を知ってから3年が経つとできない。
など、様々な事情によって答えは変わってきます。
さらに正確に言うと、
①の場合でも、婚姻関係破綻のハードルは高く、既に離婚協議をしていたとか、離婚前提で別居していた場合で無ければ、婚姻関係破綻と認定される可能性は低い。
②の場合でも、既婚者であると知らなかったことについて過失があれば、慰謝料請求できる。
など、さらに条件が加わると答えが変わってきます。
つまり、正確に法律知識を書こうとすると、どうしてもややこしい、まどろっこしい、長文になってしまうんです。
ネットでググっていると、どうしてもパッと答えを明快に書いている記事に目が移りますが、法律知識の場合むしろ長文で色々と場合分けしたり理由付けして書いている記事の方が、信用できる場合が多いんですよね。
といいながら筆者のこの記事も、グダグダと長文になってしまいました。
長文なので信用できると思ってくださいね(笑)

【滋賀県草津市の弁護士への相談はこちら】

滋賀の弁護士/草津駅前法律事務所
…このブログの筆者の事務所のメインサイト。

滋賀の弁護士による離婚相談
…離婚に関する相談サイト。

滋賀の弁護士の交通事故無料相談
…交通事故相談サイト。

個人事業・会社の破産・倒産無料相談
…会社の破産相談サイト。
司法試験をPCで受験
2023年07月18日
先日のニュースで、司法試験の筆記試験(論文式試験)について、手書きではなく、試験実施機関側が用意するPCで受験できるようになると報道されていました。
司法試験って、わざわざPCを実施期間が用意するような試験なのでしょうか?

司法試験の論文式試験は、マークシート式などと異なり、出題に対して法的に論述をしていくため、文書を書く量が膨大になります。
試験時間も、たとえば令和5年度の実施要領によれば、初日に選択科目3時間、公法系科目第1問2時間、公法系科目第2問2時間が行われ、2日目には民事系科目2時間×3問、3日目に刑事系科目2時間×2問が行われます。つまり、長い日は7時間にわたって論文を書きまくるわけで、手書きだと本当に手が痛くなります。
それでもこれまでは手書きだったため、模試の頃から、どうすれば楽に、早く、かつ読みやすい字が書けるか、ということを考えている受験生がたくさんいたんですよね。
もっとも、実際に弁護士や裁判官などの法律実務家になると、手書きで文書を書く機会はほとんどなく、ほぼPCでの文書作成になります。
そういう意味では、試験において手書きを強制させる意味はなく、試験機関側の準備は大変だとは思いますが、PCでの試験実施の方がよいと個人的には思っています
【滋賀県草津市の弁護士への相談はこちら】

滋賀の弁護士/草津駅前法律事務所
…このブログの筆者の事務所のメインサイト。

滋賀の弁護士による離婚相談
…離婚に関する相談サイト。

滋賀の弁護士の交通事故無料相談
…交通事故相談サイト。

個人事業・会社の破産・倒産無料相談
…会社の破産相談サイト。
司法試験って、わざわざPCを実施期間が用意するような試験なのでしょうか?

司法試験の論文式試験は、マークシート式などと異なり、出題に対して法的に論述をしていくため、文書を書く量が膨大になります。
試験時間も、たとえば令和5年度の実施要領によれば、初日に選択科目3時間、公法系科目第1問2時間、公法系科目第2問2時間が行われ、2日目には民事系科目2時間×3問、3日目に刑事系科目2時間×2問が行われます。つまり、長い日は7時間にわたって論文を書きまくるわけで、手書きだと本当に手が痛くなります。
それでもこれまでは手書きだったため、模試の頃から、どうすれば楽に、早く、かつ読みやすい字が書けるか、ということを考えている受験生がたくさんいたんですよね。
もっとも、実際に弁護士や裁判官などの法律実務家になると、手書きで文書を書く機会はほとんどなく、ほぼPCでの文書作成になります。
そういう意味では、試験において手書きを強制させる意味はなく、試験機関側の準備は大変だとは思いますが、PCでの試験実施の方がよいと個人的には思っています

【滋賀県草津市の弁護士への相談はこちら】

滋賀の弁護士/草津駅前法律事務所
…このブログの筆者の事務所のメインサイト。

滋賀の弁護士による離婚相談
…離婚に関する相談サイト。

滋賀の弁護士の交通事故無料相談
…交通事故相談サイト。

個人事業・会社の破産・倒産無料相談
…会社の破産相談サイト。
死後10年経つと相続に関して争うことが制限されます
2023年02月20日
相続については、「法定相続分」と言って、法律で基本となる相続の割合が示されています。相続人同士が話合いで遺産をどう分けるかを決めるのは自由ですが、話がまとまらず裁判所での争いとなった場合、法定相続割合をベースとして裁判所が遺産分割方法を決めることになります。

しかし、実際には、法定相続割合を修正する制度として、「寄与分」(=被相続人の療養看護などを行った相続人の取り分を多くする制度)や、「特別受益」(=生前贈与などを受けていた相続人の取り分を減らす制度)があり、これらの適用に関して相続人間で揉めて裁判所での争いとなることが多々あります。
ところが、今年、すなわち令和5年4月1日から、原則として死後10年以上経過すると、寄与分や特別受益で争うことができず、法定相続割合どおりに分割されることになりました。
(参考・改正民法904条の3)
第904条の3
前三条の規定(筆者注:特別受益・寄与分)は、相続開始の時から10年を経過した後にする遺産の分割については、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
①相続開始の時から10年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。
②相続開始の時から始まる10年の期間の満了前6箇月以内の間に、遺産の分割を請求することができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅した時から6箇月を経過する前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。
これは相続事件を扱う弁護士からみれば大きな影響を与える改正です。死後10年以上経ったけどまだ遺産相続の話ができていないというケースは結構あり、それなのにいざ分けるということになると、一部の相続人が寄与分や特別受益を主張して揉めるというケースは少なくありません。既に10年以上経っているので、当時の状況が曖昧だったり、証拠が少なくなっていることも多く、調停や審判で揉めに揉めることがあるんです。
これからは、そのような主張をしたいのであれば、10年以内に調停を申し立てるべきということになりますし、それ以上放っておいた案件は法定相続割合で決まるわけですから、早期に解決しやすくなります。
なお、今回の改正は、施行日である令和5年4月1日よりも前に死亡したケースにも適用されるものの、特別受益や寄与分の主張は、①相続開始の時から10年が経過するとき、または、②施行日から5年が経過するときのいずれか「遅い方」までとされていますので、少なくとも令和10年4月1日までは特別受益や寄与分の主張をすることは可能です。
法改正により、相続が発生した場合にはできるだけ早めに遺産分割の話や登記手続をすべしという条文がいくつができています。
遺産相続の話はほったらかしにせず、できるだけ早めに協議をするようにした方がよいですね
【滋賀県草津市の弁護士への相談はこちら】

滋賀の弁護士/草津駅前法律事務所
…このブログの筆者の事務所のメインサイト。

滋賀の弁護士による離婚相談
…離婚に関する相談サイト。

滋賀の弁護士の交通事故無料相談
…交通事故相談サイト。

個人事業・会社の破産・倒産無料相談
…会社の破産相談サイト。

しかし、実際には、法定相続割合を修正する制度として、「寄与分」(=被相続人の療養看護などを行った相続人の取り分を多くする制度)や、「特別受益」(=生前贈与などを受けていた相続人の取り分を減らす制度)があり、これらの適用に関して相続人間で揉めて裁判所での争いとなることが多々あります。
ところが、今年、すなわち令和5年4月1日から、原則として死後10年以上経過すると、寄与分や特別受益で争うことができず、法定相続割合どおりに分割されることになりました。
(参考・改正民法904条の3)
第904条の3
前三条の規定(筆者注:特別受益・寄与分)は、相続開始の時から10年を経過した後にする遺産の分割については、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
①相続開始の時から10年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。
②相続開始の時から始まる10年の期間の満了前6箇月以内の間に、遺産の分割を請求することができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅した時から6箇月を経過する前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。
これは相続事件を扱う弁護士からみれば大きな影響を与える改正です。死後10年以上経ったけどまだ遺産相続の話ができていないというケースは結構あり、それなのにいざ分けるということになると、一部の相続人が寄与分や特別受益を主張して揉めるというケースは少なくありません。既に10年以上経っているので、当時の状況が曖昧だったり、証拠が少なくなっていることも多く、調停や審判で揉めに揉めることがあるんです。
これからは、そのような主張をしたいのであれば、10年以内に調停を申し立てるべきということになりますし、それ以上放っておいた案件は法定相続割合で決まるわけですから、早期に解決しやすくなります。
なお、今回の改正は、施行日である令和5年4月1日よりも前に死亡したケースにも適用されるものの、特別受益や寄与分の主張は、①相続開始の時から10年が経過するとき、または、②施行日から5年が経過するときのいずれか「遅い方」までとされていますので、少なくとも令和10年4月1日までは特別受益や寄与分の主張をすることは可能です。
法改正により、相続が発生した場合にはできるだけ早めに遺産分割の話や登記手続をすべしという条文がいくつができています。
遺産相続の話はほったらかしにせず、できるだけ早めに協議をするようにした方がよいですね

【滋賀県草津市の弁護士への相談はこちら】

滋賀の弁護士/草津駅前法律事務所
…このブログの筆者の事務所のメインサイト。

滋賀の弁護士による離婚相談
…離婚に関する相談サイト。

滋賀の弁護士の交通事故無料相談
…交通事故相談サイト。

個人事業・会社の破産・倒産無料相談
…会社の破産相談サイト。
相続放棄をした人の責任が大きく変わります
2023年02月02日
相続放棄をすると、亡くなった人の負債を支払う必要がなくなり、義務を履行する必要がありません。
ところが、これまでの民法では、相続放棄をしても管理義務を負うことがあり、それが今年4月1日からルールが大きく変わるって知っていますか?

改正前民法940条1項では、相続放棄をしても、次の相続人が遺産の管理を始めるまでは、相続放棄をした者が管理を継続しなければならないとされていました。
たとえば、親が田舎に崩れそうなボロボロの空き家を所有しており、管理が大変なので相続放棄をしても、次の相続人が遺産の管理をするまで、ボロボロの空き家が近隣に迷惑を掛けないよう、管理をする義務があるのです。
そして、この条文上では、相続人全員が相続放棄をした場合、誰が管理義務を負うのかが明確ではありませんでした。
(参考 改正前民法940条1項)
相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。
この点、令和5年4月1日から施行される改正後の民法940条1項では、相続放棄のときに現に占有している財産についてのみ、管理義務を負うと規定されました。したがって、これまで一切占有をしたことが無いような田舎の空き家であれば、管理義務を負わないことになります。
(参考 改正後民法940条1項)
相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。
これは、弁護士実務において結構重要な改正なんです。これまで、改正前の条文があるせいで、「相続放棄をしたら責任負いませんよね?」という相談に対しても、「でも、一応管理義務は継続しますから…」という答えにならざるを得ませんでしたが、今後は占有していなければ、管理義務はないと答えることができます。
ただし、「占有」というのは、直接的にその場所を利用したり支配している場合だけでなく、間接的に支配していると言える場合にも成立し得ます。たとえば、空き家の鍵を持っていて、盆と正月だけは草刈りなどに帰っていた、という場合でも、占有が認められることがありますので、注意が必要かと思います
【滋賀県草津市の弁護士への相談はこちら】

滋賀の弁護士/草津駅前法律事務所
…このブログの筆者の事務所のメインサイト。

滋賀の弁護士による離婚相談
…離婚に関する相談サイト。

滋賀の弁護士の交通事故無料相談
…交通事故相談サイト。

個人事業・会社の破産・倒産無料相談
…会社の破産相談サイト。
ところが、これまでの民法では、相続放棄をしても管理義務を負うことがあり、それが今年4月1日からルールが大きく変わるって知っていますか?

改正前民法940条1項では、相続放棄をしても、次の相続人が遺産の管理を始めるまでは、相続放棄をした者が管理を継続しなければならないとされていました。
たとえば、親が田舎に崩れそうなボロボロの空き家を所有しており、管理が大変なので相続放棄をしても、次の相続人が遺産の管理をするまで、ボロボロの空き家が近隣に迷惑を掛けないよう、管理をする義務があるのです。
そして、この条文上では、相続人全員が相続放棄をした場合、誰が管理義務を負うのかが明確ではありませんでした。
(参考 改正前民法940条1項)
相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。
この点、令和5年4月1日から施行される改正後の民法940条1項では、相続放棄のときに現に占有している財産についてのみ、管理義務を負うと規定されました。したがって、これまで一切占有をしたことが無いような田舎の空き家であれば、管理義務を負わないことになります。
(参考 改正後民法940条1項)
相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。
これは、弁護士実務において結構重要な改正なんです。これまで、改正前の条文があるせいで、「相続放棄をしたら責任負いませんよね?」という相談に対しても、「でも、一応管理義務は継続しますから…」という答えにならざるを得ませんでしたが、今後は占有していなければ、管理義務はないと答えることができます。
ただし、「占有」というのは、直接的にその場所を利用したり支配している場合だけでなく、間接的に支配していると言える場合にも成立し得ます。たとえば、空き家の鍵を持っていて、盆と正月だけは草刈りなどに帰っていた、という場合でも、占有が認められることがありますので、注意が必要かと思います

【滋賀県草津市の弁護士への相談はこちら】

滋賀の弁護士/草津駅前法律事務所
…このブログの筆者の事務所のメインサイト。

滋賀の弁護士による離婚相談
…離婚に関する相談サイト。

滋賀の弁護士の交通事故無料相談
…交通事故相談サイト。

個人事業・会社の破産・倒産無料相談
…会社の破産相談サイト。
オリンピックの契約書
2021年07月16日
来週から始まるにもかかわらず、いまだに中止とか反対の声も多く、観客についても不安定な情勢ですが、実は開催地である日本・東京と、IOCとの間でどのような契約になっているのか、ネットで公開されているって知っていますか?

ネットでググればすぐに出てきますが、「開催都市契約」という、日本オリンピック委員会、東京都とIOCとの間の契約書が公開されています。
法律家の目線で見たときにまず驚くのは、契約解除の条項に関して、あくまで契約解除(大会中止)ができるのはIOC側のみという点です。
つまり、日本や東京都からは、契約解除、つまり大会中止を求める権利はないんですよね。
しかも、IOCが契約解除を決めても、日本や東京都からは一切損害賠償の請求はできない上、もし中止によって第三者がIOCに損害賠償請求をした場合でも、日本側がIOCを「補償」し、「無害に保つものとする」とされています(開催都市契約66条)。
これが通常の企業間の契約なら、顧問弁護士としては「これは不公平すぎる!」と思わず署名押印にストップをかけたくなる契約内容なのですが、やはりオリンピックの開催という1大ムーブメントとなると、致し方ないことなんでしょうかねえ。
こういう特殊な契約書を見る機会ってなかなかないので、司法修習生やロースクール生のみなさんは、ぜひこの機会に内容を見てみると興味深いかもしれませんね
(なお、筆者は契約内容の全てを精査したわけではなく、他の条項や契約によって、上記とは異なる合意や条項があるかもしれませんし、上記はあくまで筆者の個人的な意見。感想ですので、ご了承ください)
【滋賀県草津市の弁護士への相談はこちら】

滋賀の弁護士/草津駅前法律事務所
…このブログの筆者の事務所のメインサイト。

滋賀の弁護士による離婚相談
…離婚に関する相談サイト。

滋賀の弁護士の交通事故無料相談
…交通事故相談サイト。

個人事業・会社の破産・倒産無料相談
…会社の破産相談サイト。

ネットでググればすぐに出てきますが、「開催都市契約」という、日本オリンピック委員会、東京都とIOCとの間の契約書が公開されています。
法律家の目線で見たときにまず驚くのは、契約解除の条項に関して、あくまで契約解除(大会中止)ができるのはIOC側のみという点です。
つまり、日本や東京都からは、契約解除、つまり大会中止を求める権利はないんですよね。
しかも、IOCが契約解除を決めても、日本や東京都からは一切損害賠償の請求はできない上、もし中止によって第三者がIOCに損害賠償請求をした場合でも、日本側がIOCを「補償」し、「無害に保つものとする」とされています(開催都市契約66条)。
これが通常の企業間の契約なら、顧問弁護士としては「これは不公平すぎる!」と思わず署名押印にストップをかけたくなる契約内容なのですが、やはりオリンピックの開催という1大ムーブメントとなると、致し方ないことなんでしょうかねえ。
こういう特殊な契約書を見る機会ってなかなかないので、司法修習生やロースクール生のみなさんは、ぜひこの機会に内容を見てみると興味深いかもしれませんね

(なお、筆者は契約内容の全てを精査したわけではなく、他の条項や契約によって、上記とは異なる合意や条項があるかもしれませんし、上記はあくまで筆者の個人的な意見。感想ですので、ご了承ください)
【滋賀県草津市の弁護士への相談はこちら】

滋賀の弁護士/草津駅前法律事務所
…このブログの筆者の事務所のメインサイト。

滋賀の弁護士による離婚相談
…離婚に関する相談サイト。

滋賀の弁護士の交通事故無料相談
…交通事故相談サイト。

個人事業・会社の破産・倒産無料相談
…会社の破産相談サイト。
モラルハラスメントって難しい?
2021年07月13日
セクハラやパワハラなど、色々なハラスメントがありますが、最近特に離婚相談などの場面で、「モラルハラスメント」の主張が増えてきています。
でも実は、何がモラルハラスメントにあたるのかって、明確にするのは難しいって知っていますか?

本来、不法行為というのは、加害者側に故意または過失が必要とされています。被害者がどう思ったのかというよりは、加害者の主観が重要なのです。
他方で、ハラスメントという概念は、被害者側の感情を重視する側面があります。
たとえば、みすぼらしい男性上司Aと、福山雅治似の男性上司Bが、別々の機会に、同じ女性新入社員に、「今日2人でご飯を食べに行こう」と背中を触って執拗に誘ったとします。
男性上司Aも、男性上司Bも、いずれも心の底から「彼女は最近悩んでいる様子だから、話を聞いてあげよう」と思っていただけだとします。
このときに、女性新入社員が、男性上司Aに対しては嫌悪感を示し、福山雅治似の男性上司Bに対しては喜んだ場合、同じ行為なのにAだけがセクハラにあたる可能性があるんです。それは、ハラスメントが、「被害者が嫌がるかどうか」を重要な要素としているからなんです。
そのため、ハラスメントという概念は曖昧に広がる可能性があるため、違法とされるのは、「セクシャル(性的な)」ハラスメントや、「パワー(地位を利用した)」ハラスメントなどに限定されてきます。
ところが、「モラル」というのは倫理観のことで、相手が嫌がること全般がモラルハラスメントに該当する可能性があります。
たとえば夫婦間で、夫は好意で「僕が子どもの塾の送り迎えをするよ」と妻に言っていたとしても、妻は「私が送り迎えをしたいのに、そんなことを言ってくるのはモラハラだ」と主張してくるケースなどもあるんです。何がモラルハラスメントになるのかって、結構判断が難しいことが多いんですよね。
ネット上では、「モラハラ」というワードが飛び交っていますが、実際に「モラハラ」だけを真正面から認定して慰謝料や離婚原因が認められた裁判例って、意外と少ないです。裁判官としても、何が「モラル」に反するのかを判決書で断定するのは、できれば避けたいと思っているのかもしれませんね
【滋賀県草津市の弁護士への相談はこちら】

滋賀の弁護士/草津駅前法律事務所
…このブログの筆者の事務所のメインサイト。

滋賀の弁護士による離婚相談
…離婚に関する相談サイト。

滋賀の弁護士の交通事故無料相談
…交通事故相談サイト。

個人事業・会社の破産・倒産無料相談
…会社の破産相談サイト。
でも実は、何がモラルハラスメントにあたるのかって、明確にするのは難しいって知っていますか?

本来、不法行為というのは、加害者側に故意または過失が必要とされています。被害者がどう思ったのかというよりは、加害者の主観が重要なのです。
他方で、ハラスメントという概念は、被害者側の感情を重視する側面があります。
たとえば、みすぼらしい男性上司Aと、福山雅治似の男性上司Bが、別々の機会に、同じ女性新入社員に、「今日2人でご飯を食べに行こう」と背中を触って執拗に誘ったとします。
男性上司Aも、男性上司Bも、いずれも心の底から「彼女は最近悩んでいる様子だから、話を聞いてあげよう」と思っていただけだとします。
このときに、女性新入社員が、男性上司Aに対しては嫌悪感を示し、福山雅治似の男性上司Bに対しては喜んだ場合、同じ行為なのにAだけがセクハラにあたる可能性があるんです。それは、ハラスメントが、「被害者が嫌がるかどうか」を重要な要素としているからなんです。
そのため、ハラスメントという概念は曖昧に広がる可能性があるため、違法とされるのは、「セクシャル(性的な)」ハラスメントや、「パワー(地位を利用した)」ハラスメントなどに限定されてきます。
ところが、「モラル」というのは倫理観のことで、相手が嫌がること全般がモラルハラスメントに該当する可能性があります。
たとえば夫婦間で、夫は好意で「僕が子どもの塾の送り迎えをするよ」と妻に言っていたとしても、妻は「私が送り迎えをしたいのに、そんなことを言ってくるのはモラハラだ」と主張してくるケースなどもあるんです。何がモラルハラスメントになるのかって、結構判断が難しいことが多いんですよね。
ネット上では、「モラハラ」というワードが飛び交っていますが、実際に「モラハラ」だけを真正面から認定して慰謝料や離婚原因が認められた裁判例って、意外と少ないです。裁判官としても、何が「モラル」に反するのかを判決書で断定するのは、できれば避けたいと思っているのかもしれませんね

【滋賀県草津市の弁護士への相談はこちら】

滋賀の弁護士/草津駅前法律事務所
…このブログの筆者の事務所のメインサイト。

滋賀の弁護士による離婚相談
…離婚に関する相談サイト。

滋賀の弁護士の交通事故無料相談
…交通事故相談サイト。

個人事業・会社の破産・倒産無料相談
…会社の破産相談サイト。
法律は弱い立場の人を助けてくれない?
2021年07月06日
法律相談をしていると、「法律は結局立場の弱い人を助けてくれないんですね」と言われてしまうことがたまにあります。
実際に、法律は弱い立場の人を助けてくれないものなんでしょうか?

個別の法律によっても異なりますが、特に一般消費者・エンドユーザーに関する法律について言えば、基本的には専門知識が少なく立場が弱い一般消費者・エンドユーザーを守ろうという法律が多いです。たとえば、消費者契約法ですと、事業者側に規制をかけて消費者を守ろうとしていますし、借地借家法ですと、様々な条文で賃借人側は民法以上に保護をされています。
ただ、それでも、「証拠がなければ結局法律でも救われない」というケースが結構あるなと感じます。
たとえば、悪徳業者に支払わなくてもいいお金を支払ってしまった、というケースでも、振込の記録や領収証が残っていれば法律で救われる可能性があっても、現金手渡しや、領収証を捨ててしまっていると、支払の事実が立証できず、救済されないということがありえます。
また、上司からのパワハラ被害を訴えたいとしても、録音やメールなど、パワハラを立証する証拠がないと、被害回復は難しいことが多いでしょう。
ということで、法律自体が弱い立場の人を助けてくれないというよりは、証拠がないことによって結局は法律でも救済されない、というケースの方が多い気がします。
とはいっても、紛争になる前から証拠確保を意識しておくってなかなか難しいんですよね
【滋賀県草津市の弁護士への相談はこちら】

滋賀の弁護士/草津駅前法律事務所
…このブログの筆者の事務所のメインサイト。

滋賀の弁護士による離婚相談
…離婚に関する相談サイト。

滋賀の弁護士の交通事故無料相談
…交通事故相談サイト。

個人事業・会社の破産・倒産無料相談
…会社の破産相談サイト。
実際に、法律は弱い立場の人を助けてくれないものなんでしょうか?

個別の法律によっても異なりますが、特に一般消費者・エンドユーザーに関する法律について言えば、基本的には専門知識が少なく立場が弱い一般消費者・エンドユーザーを守ろうという法律が多いです。たとえば、消費者契約法ですと、事業者側に規制をかけて消費者を守ろうとしていますし、借地借家法ですと、様々な条文で賃借人側は民法以上に保護をされています。
ただ、それでも、「証拠がなければ結局法律でも救われない」というケースが結構あるなと感じます。
たとえば、悪徳業者に支払わなくてもいいお金を支払ってしまった、というケースでも、振込の記録や領収証が残っていれば法律で救われる可能性があっても、現金手渡しや、領収証を捨ててしまっていると、支払の事実が立証できず、救済されないということがありえます。
また、上司からのパワハラ被害を訴えたいとしても、録音やメールなど、パワハラを立証する証拠がないと、被害回復は難しいことが多いでしょう。
ということで、法律自体が弱い立場の人を助けてくれないというよりは、証拠がないことによって結局は法律でも救済されない、というケースの方が多い気がします。
とはいっても、紛争になる前から証拠確保を意識しておくってなかなか難しいんですよね

【滋賀県草津市の弁護士への相談はこちら】

滋賀の弁護士/草津駅前法律事務所
…このブログの筆者の事務所のメインサイト。

滋賀の弁護士による離婚相談
…離婚に関する相談サイト。

滋賀の弁護士の交通事故無料相談
…交通事故相談サイト。

個人事業・会社の破産・倒産無料相談
…会社の破産相談サイト。
タグ :法律
ネットで目にする判例って一般的ではない?
2021年02月25日
たまに、相談者の方が、「インターネットでこんな裁判例が載っていたんですよ!だから私のケースでもこれはいけるんじゃないですか!?」と聞いてこられる場合があります。
ただ実は、ネットや判例雑誌に掲載される裁判例って、一般的なものではないことも多いって知っていますか?

たとえば、離婚の財産分与って、原則として夫と妻で2分の1ずつの折半なんですよね。でも、それって法律実務家にとっては当たり前に近いルールなんで、2分の1ずつ財産分与するという判決や審判が出ても、今さら話題にはなりませんし、判例雑誌などに特に掲載されるわけではありません。
他方で、何らかの特殊事情で2分の1という原則が修正された判決や審判が出た場合、珍しいので判例雑誌に掲載されたり、ネットで記事になったりするんですよね。
ところが、このどういう特殊事情があったのかという点について、ネットの記事などではごく簡単にしか記載されていないので、それを見た人からすれば、「なんだ、財産分与って2分の1とは限らないんだ!」とか、「私のケースでも当てはまるはずだ!」と勘違いしてしまいやすいんですよね。
ですので、ネットで判例をみつけたとしても、非常に珍しいケースであることも多いので、それが自分のケースに当てはまるのかどうかは、弁護士にしっかりと相談されることを強くお勧めします
【滋賀県草津市の弁護士への相談はこちら】

滋賀の弁護士/草津駅前法律事務所
…このブログの筆者の事務所のメインサイト。

滋賀の弁護士による離婚相談
…離婚に関する相談サイト。

滋賀の弁護士の交通事故無料相談
…交通事故相談サイト。

個人事業・会社の破産・倒産無料相談
…会社の破産相談サイト。
ただ実は、ネットや判例雑誌に掲載される裁判例って、一般的なものではないことも多いって知っていますか?

たとえば、離婚の財産分与って、原則として夫と妻で2分の1ずつの折半なんですよね。でも、それって法律実務家にとっては当たり前に近いルールなんで、2分の1ずつ財産分与するという判決や審判が出ても、今さら話題にはなりませんし、判例雑誌などに特に掲載されるわけではありません。
他方で、何らかの特殊事情で2分の1という原則が修正された判決や審判が出た場合、珍しいので判例雑誌に掲載されたり、ネットで記事になったりするんですよね。
ところが、このどういう特殊事情があったのかという点について、ネットの記事などではごく簡単にしか記載されていないので、それを見た人からすれば、「なんだ、財産分与って2分の1とは限らないんだ!」とか、「私のケースでも当てはまるはずだ!」と勘違いしてしまいやすいんですよね。
ですので、ネットで判例をみつけたとしても、非常に珍しいケースであることも多いので、それが自分のケースに当てはまるのかどうかは、弁護士にしっかりと相談されることを強くお勧めします

【滋賀県草津市の弁護士への相談はこちら】

滋賀の弁護士/草津駅前法律事務所
…このブログの筆者の事務所のメインサイト。

滋賀の弁護士による離婚相談
…離婚に関する相談サイト。

滋賀の弁護士の交通事故無料相談
…交通事故相談サイト。

個人事業・会社の破産・倒産無料相談
…会社の破産相談サイト。
ネットの回答は信用できないの?
2020年12月11日
様々な法律問題について、今やネットでちょっとググれば答えっぽいものが出てきますし、無料の質問板みたいなものもたくさんあります。
それでも、弁護士に相談料を払って「法律相談」をする意味ってどれくらいあるのでしょうか?

結論から言えば、どれだけネットで調べても、真剣に困っている法律問題であれば、弁護士に相談する意味は十二分にあると思います。
法律問題って、「前提となる事実」が違うと、答えや解決方法が全くことなってくるんです。
たとえば、
Q:夫が不倫しています。相手の女に慰謝料請求できますか?
という質問に対し、前提事実を思いっきりすっ飛ばして単純化すれば、
A:はい、できます。
になるのでしょう。
ところが、上記と同じ質問でも、以下のように前提事実が異なるだけで、回答が大きく異なってきます。
①相手の女は夫が既婚者であると全く知りませんでした。
→原則として慰謝料請求できません。
②相手の女は夫が既婚者と知りませんでしたが、知ることが容易にできました。
→女に過失があれば慰謝料請求できます。
③夫から既に多額の慰謝料をもらっています。
→女に対する請求は認められない可能性が高いです。
④不倫と言っても、肉体関係はなく、プラトニックな関係だったようです。
→原則として慰謝料請求はできません。
⑤夫とは既に別居期間が長く、離婚調停中でした。
→慰謝料請求が認められない可能性があります。
⑥夫よりも先に私が不倫をしていました。
→事情によりますが、慰謝料請求はできない可能性があります。
⑦女には全く財産はありません。
→請求ができても、実際の回収は困難な場合があります。
⑧肉体関係の証拠がなく、女は否定しています。
→このまま請求をしても、立証が難しいです。
上記①から⑧は、ほとんど何も考えずに、3分くらいでざっと書き連ねましたが、弁護士が実際に相談者と会って法律相談をする場合、単に冒頭のQとAだけでなく、上記のような例外事由がないかなどを相談の中で慎重に吟味するんですよね。実際には、もっともっと検討するポイントはあります。
ところが、自分でネットで検索しても、自分自身と全く同じ事案はそうそうないでしょうから、それが本当に自分に当てはまる答えかどうかはわかりません。
また、無料の法律相談掲示板であったり、弁護士とのメール相談では、全ての前提事実を伝えるのは非常に困難です。
他方で、その分野に熟練した弁護士であれば、相談者と1時間実際に会って話をすれば、その中でおそらくメールでの質問の10倍近い情報を聞き出して、また、重要な情報については聞き方を変えたりして核心を引き出し、その上でアドバイスをするため、ネット検索やネットの掲示板での回答よりもずっと的確な回答になることが多いんです。
というわけで、本当に法律問題で困ったときは、ずーっとネットでググり続けるのではなく、弁護士に実際に会って相談をされることをお勧めします。相談料がかかっても、誤った情報で最終的な結果に悪影響を与えるよりは、ずっと費用対効果は高いことが多いと思いますよ
【滋賀県草津市の弁護士への相談はこちら】

滋賀の弁護士/草津駅前法律事務所
…このブログの筆者の事務所のメインサイト。

滋賀の弁護士による離婚相談
…離婚に関する相談サイト。

滋賀の弁護士の交通事故無料相談
…交通事故相談サイト。

個人事業・会社の破産・倒産無料相談
…会社の破産相談サイト。
それでも、弁護士に相談料を払って「法律相談」をする意味ってどれくらいあるのでしょうか?

結論から言えば、どれだけネットで調べても、真剣に困っている法律問題であれば、弁護士に相談する意味は十二分にあると思います。
法律問題って、「前提となる事実」が違うと、答えや解決方法が全くことなってくるんです。
たとえば、
Q:夫が不倫しています。相手の女に慰謝料請求できますか?
という質問に対し、前提事実を思いっきりすっ飛ばして単純化すれば、
A:はい、できます。
になるのでしょう。
ところが、上記と同じ質問でも、以下のように前提事実が異なるだけで、回答が大きく異なってきます。
①相手の女は夫が既婚者であると全く知りませんでした。
→原則として慰謝料請求できません。
②相手の女は夫が既婚者と知りませんでしたが、知ることが容易にできました。
→女に過失があれば慰謝料請求できます。
③夫から既に多額の慰謝料をもらっています。
→女に対する請求は認められない可能性が高いです。
④不倫と言っても、肉体関係はなく、プラトニックな関係だったようです。
→原則として慰謝料請求はできません。
⑤夫とは既に別居期間が長く、離婚調停中でした。
→慰謝料請求が認められない可能性があります。
⑥夫よりも先に私が不倫をしていました。
→事情によりますが、慰謝料請求はできない可能性があります。
⑦女には全く財産はありません。
→請求ができても、実際の回収は困難な場合があります。
⑧肉体関係の証拠がなく、女は否定しています。
→このまま請求をしても、立証が難しいです。
上記①から⑧は、ほとんど何も考えずに、3分くらいでざっと書き連ねましたが、弁護士が実際に相談者と会って法律相談をする場合、単に冒頭のQとAだけでなく、上記のような例外事由がないかなどを相談の中で慎重に吟味するんですよね。実際には、もっともっと検討するポイントはあります。
ところが、自分でネットで検索しても、自分自身と全く同じ事案はそうそうないでしょうから、それが本当に自分に当てはまる答えかどうかはわかりません。
また、無料の法律相談掲示板であったり、弁護士とのメール相談では、全ての前提事実を伝えるのは非常に困難です。
他方で、その分野に熟練した弁護士であれば、相談者と1時間実際に会って話をすれば、その中でおそらくメールでの質問の10倍近い情報を聞き出して、また、重要な情報については聞き方を変えたりして核心を引き出し、その上でアドバイスをするため、ネット検索やネットの掲示板での回答よりもずっと的確な回答になることが多いんです。
というわけで、本当に法律問題で困ったときは、ずーっとネットでググり続けるのではなく、弁護士に実際に会って相談をされることをお勧めします。相談料がかかっても、誤った情報で最終的な結果に悪影響を与えるよりは、ずっと費用対効果は高いことが多いと思いますよ

【滋賀県草津市の弁護士への相談はこちら】

滋賀の弁護士/草津駅前法律事務所
…このブログの筆者の事務所のメインサイト。

滋賀の弁護士による離婚相談
…離婚に関する相談サイト。

滋賀の弁護士の交通事故無料相談
…交通事故相談サイト。

個人事業・会社の破産・倒産無料相談
…会社の破産相談サイト。
体温が高い人に対しても、旅館やホテルは宿泊拒否できない?
2020年10月12日
旅館やホテルにおいて、新型コロナウイルス対策として、チェックイン時に検温をし、37.5度以上であれば宿泊を控えてもらう、という対応をしている旅館・ホテルが増えてきていると思います。
しかしながら、実はこのような場合でも旅館やホテル側が宿泊拒否をすると「違法」になる可能性があるって知っていますか?

旅館業法という、昭和23年に制定された法律では、5条において宿泊拒否をしてはならないことが定められています。
第5条 営業者は、左の各号の一に該当する場合を除いては、宿泊を拒んではならない。
一 宿泊しようとする者が伝染性の疾病にかかつていると明らかに認められるとき。
二 宿泊しようとする者がとばく、その他の違法行為又は風紀を乱す行為をする虞があると認められるとき。
三 宿泊施設に余裕がないときその他都道府県が条例で定める事由があるとき。
伝染病にかかっている疑いがあるだけでは宿泊拒否できず、「明らかに認められるとき」でなければダメなんですよね。
そして、この規定は強行法規であると考えられているため、当事者間の契約や事前の告知で除外はできないと考えられています。
つまり、予約申込時に、「うちの旅館はチェックイン時に体温が高い方は宿泊できません」と明記していたとしても、そもそもそのような明記自体が旅館業法5条に違反すると考えられるのです。
したがって、この旅館業法の規定に従えば、ホテルや旅館としては、体温が高い人についてあくまで宿泊を控えて頂くよう「お願い」することしかできず、それでも泊めろという人に宿泊拒否をすることは現状ではなかなか難しいということになります。
ただ、この旅館業法の規定は、これまでも何度も改正・撤廃すべきという声があがっています。
宿泊客のニーズも多様化し、それに応える宿泊施設も多様化しています。「うちは●●の顧客のみ受け付けますよ」というような、特定の客層のみを受け付ける宿泊施設があってもよいように思われます。
旅館業法の規定は、この法律が制定された戦後の頃は、宿泊施設は社会的・公共的施設という側面が強く、また、人を選別して宿泊拒否が行われると、差別につながるから、ということも制定の理由にあったのかもしれません。しかし、宿泊施設が増え、ネットで簡単に予約ができる現在において、果たしてこの規定のままでよいのかは疑問が残ります。
なお、現状の規定でも、たとえば非常に高熱があるとか、新型コロナが非常に蔓延している地域で新型コロナ特有の症状が出ているとかであれば、「伝染性の疾病にかかっていると明らかに認められる」という範疇に入る可能性もありうるかもしれません。
また、宿泊拒否ができないからといって、「ちょっとくらい熱があっても泊まっていいや」などという考えで行動することは、たとえ法律違反ではないにせよ、社会的・道義的には好ましくないでしょう。
ホテル・旅館からの相談を受ける弁護士の立場からすれば、新型コロナの問題を機に、旅館業法(5条)の改正に向けて動きがあればいいなと思っています。
しかしながら、実はこのような場合でも旅館やホテル側が宿泊拒否をすると「違法」になる可能性があるって知っていますか?

旅館業法という、昭和23年に制定された法律では、5条において宿泊拒否をしてはならないことが定められています。
第5条 営業者は、左の各号の一に該当する場合を除いては、宿泊を拒んではならない。
一 宿泊しようとする者が伝染性の疾病にかかつていると明らかに認められるとき。
二 宿泊しようとする者がとばく、その他の違法行為又は風紀を乱す行為をする虞があると認められるとき。
三 宿泊施設に余裕がないときその他都道府県が条例で定める事由があるとき。
伝染病にかかっている疑いがあるだけでは宿泊拒否できず、「明らかに認められるとき」でなければダメなんですよね。
そして、この規定は強行法規であると考えられているため、当事者間の契約や事前の告知で除外はできないと考えられています。
つまり、予約申込時に、「うちの旅館はチェックイン時に体温が高い方は宿泊できません」と明記していたとしても、そもそもそのような明記自体が旅館業法5条に違反すると考えられるのです。
したがって、この旅館業法の規定に従えば、ホテルや旅館としては、体温が高い人についてあくまで宿泊を控えて頂くよう「お願い」することしかできず、それでも泊めろという人に宿泊拒否をすることは現状ではなかなか難しいということになります。
ただ、この旅館業法の規定は、これまでも何度も改正・撤廃すべきという声があがっています。
宿泊客のニーズも多様化し、それに応える宿泊施設も多様化しています。「うちは●●の顧客のみ受け付けますよ」というような、特定の客層のみを受け付ける宿泊施設があってもよいように思われます。
旅館業法の規定は、この法律が制定された戦後の頃は、宿泊施設は社会的・公共的施設という側面が強く、また、人を選別して宿泊拒否が行われると、差別につながるから、ということも制定の理由にあったのかもしれません。しかし、宿泊施設が増え、ネットで簡単に予約ができる現在において、果たしてこの規定のままでよいのかは疑問が残ります。
なお、現状の規定でも、たとえば非常に高熱があるとか、新型コロナが非常に蔓延している地域で新型コロナ特有の症状が出ているとかであれば、「伝染性の疾病にかかっていると明らかに認められる」という範疇に入る可能性もありうるかもしれません。
また、宿泊拒否ができないからといって、「ちょっとくらい熱があっても泊まっていいや」などという考えで行動することは、たとえ法律違反ではないにせよ、社会的・道義的には好ましくないでしょう。
ホテル・旅館からの相談を受ける弁護士の立場からすれば、新型コロナの問題を機に、旅館業法(5条)の改正に向けて動きがあればいいなと思っています。
GoToトラベルキャンペーンと法的問題
2020年07月20日
宿泊代金や旅行代金の割引や助成が受けられる「GoToトラベルキャンペーン」。今様々な批判や意見がなされていますが、弁護士から見ると、様々な法的なトラブルが起こりえそうな点を感じるのですが、どういったものかわかりますか?
(以下、法律的な見解はあくまで筆者の私見であり、また、記事掲載時の報道等を前提としたものですので、正確性には十分ご留意ください。)

報道によれば、宿泊業者にはチェックイン時の検温を義務づけて、実施しない業者は登録から外す、という方針をとるようです。
では、実際に食事付きの高級旅館に宿泊に来られて、チェックイン時に体温が高いときに、旅館は強制的に宿泊拒否ができる権限があるのかが問題になります。
この点は、国交省のモデル宿泊約款第7条1項4号では、「宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき」には宿泊契約を解除できるとされています。本来は、体温が高いだけでは「明らかに認められる」とは言えませんが、コロナ渦の現状と、政府が体温(特に37.5℃以上)を一つの目安としている状況からすれば、体温37.5℃以上の場合には、この約款を根拠として旅館側が宿泊拒否できるのではないかと考えられます。
次に、その場合に、宿泊者にキャンセル料は一切かからないのでしょうか。もしそうならば、旅館としてはせっかくの部屋が無駄になる上、食事等も無駄になってしまいます。
この点、宿泊者側がキャンセルをしたわけではありませんし、また、体温が高いことについては一般的には宿泊者側の故意・過失とまでは言いがたいと思われますから、宿泊者にキャンセル料は一切かからないと考えられます。
そうすると、残念ながら、旅館としては無駄になった部屋や食事代は負担せざるを得ないでしょう。
ただ、宿泊前日に、宿泊予定者から「熱があるので明日はキャンセルしたい」と申し出た場合のキャンセル料については微妙なところです。不合理かもしれませんが、この場合には、宿泊予定者の「キャンセル申し出」によりキャンセルとなるわけですので、当日の検温時の宿泊拒否と異なり、約款上は宿泊者にキャンセル料の支払い義務が生じると言えそうです。
さらに、たとえば父・母・子3人の5人家族で旅行に来ていたとして、チェックイン時に父の発熱が判明したとします。ところが、子どもが「せっかく来たのに帰りたくない」と泣き出したため、家族で話し合い、旅館に対して「父は帰るが、母と子どもは熱がないので宿泊します」と言ってきました。
旅館としては、もし父が新型コロナだった場合、当然母と子どもらも濃厚接触者であるため、宿泊拒否したいのですが、できるのでしょうか。
この点ついては、法的な判断は非常に難しいです。純粋にモデル宿泊約款の解釈からすれば、発熱のない家族まで「伝染病者であると明らかに認められる」と拡大解釈するのは困難でしょう。そうすると、家族が泊まりたいという以上、宿泊させなくてはなりません。
ただ、もし本当に父が新型コロナに感染していたとすれば、旅館としても他の宿泊者らへの感染の危険が生じてしまうことになります。
こういった事態を避けるため、GoToトラベルキャンペーンの実施にあたり、検温を義務づけるのであれば、政府が何らかの解釈指針や対応のガイドラインを設けるべきなのではないいかと個人的には思います。モデル宿泊約款のあくまで解釈論であれば、立法までしなくても、政府の指針が一つの対応の目安にはなってくると思われます。
考え出すと色々な法的トラブルが起こりそうな今回のGoToトラベルキャンペーン。現場で頑張っている宿泊業者のためにも、政府がトラブル防止のためにやるべきことをしっかりとやって欲しいものです
【滋賀県草津市の弁護士への相談はこちら】

滋賀の弁護士/草津駅前法律事務所
…このブログの筆者の事務所のメインサイト。

滋賀の弁護士による離婚相談
…離婚に関する相談サイト。

滋賀の弁護士の交通事故無料相談
…交通事故相談サイト。

個人事業・会社の破産・倒産無料相談
…会社の破産相談サイト。
(以下、法律的な見解はあくまで筆者の私見であり、また、記事掲載時の報道等を前提としたものですので、正確性には十分ご留意ください。)

報道によれば、宿泊業者にはチェックイン時の検温を義務づけて、実施しない業者は登録から外す、という方針をとるようです。
では、実際に食事付きの高級旅館に宿泊に来られて、チェックイン時に体温が高いときに、旅館は強制的に宿泊拒否ができる権限があるのかが問題になります。
この点は、国交省のモデル宿泊約款第7条1項4号では、「宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき」には宿泊契約を解除できるとされています。本来は、体温が高いだけでは「明らかに認められる」とは言えませんが、コロナ渦の現状と、政府が体温(特に37.5℃以上)を一つの目安としている状況からすれば、体温37.5℃以上の場合には、この約款を根拠として旅館側が宿泊拒否できるのではないかと考えられます。
次に、その場合に、宿泊者にキャンセル料は一切かからないのでしょうか。もしそうならば、旅館としてはせっかくの部屋が無駄になる上、食事等も無駄になってしまいます。
この点、宿泊者側がキャンセルをしたわけではありませんし、また、体温が高いことについては一般的には宿泊者側の故意・過失とまでは言いがたいと思われますから、宿泊者にキャンセル料は一切かからないと考えられます。
そうすると、残念ながら、旅館としては無駄になった部屋や食事代は負担せざるを得ないでしょう。
ただ、宿泊前日に、宿泊予定者から「熱があるので明日はキャンセルしたい」と申し出た場合のキャンセル料については微妙なところです。不合理かもしれませんが、この場合には、宿泊予定者の「キャンセル申し出」によりキャンセルとなるわけですので、当日の検温時の宿泊拒否と異なり、約款上は宿泊者にキャンセル料の支払い義務が生じると言えそうです。
さらに、たとえば父・母・子3人の5人家族で旅行に来ていたとして、チェックイン時に父の発熱が判明したとします。ところが、子どもが「せっかく来たのに帰りたくない」と泣き出したため、家族で話し合い、旅館に対して「父は帰るが、母と子どもは熱がないので宿泊します」と言ってきました。
旅館としては、もし父が新型コロナだった場合、当然母と子どもらも濃厚接触者であるため、宿泊拒否したいのですが、できるのでしょうか。
この点ついては、法的な判断は非常に難しいです。純粋にモデル宿泊約款の解釈からすれば、発熱のない家族まで「伝染病者であると明らかに認められる」と拡大解釈するのは困難でしょう。そうすると、家族が泊まりたいという以上、宿泊させなくてはなりません。
ただ、もし本当に父が新型コロナに感染していたとすれば、旅館としても他の宿泊者らへの感染の危険が生じてしまうことになります。
こういった事態を避けるため、GoToトラベルキャンペーンの実施にあたり、検温を義務づけるのであれば、政府が何らかの解釈指針や対応のガイドラインを設けるべきなのではないいかと個人的には思います。モデル宿泊約款のあくまで解釈論であれば、立法までしなくても、政府の指針が一つの対応の目安にはなってくると思われます。
考え出すと色々な法的トラブルが起こりそうな今回のGoToトラベルキャンペーン。現場で頑張っている宿泊業者のためにも、政府がトラブル防止のためにやるべきことをしっかりとやって欲しいものです

【滋賀県草津市の弁護士への相談はこちら】

滋賀の弁護士/草津駅前法律事務所
…このブログの筆者の事務所のメインサイト。

滋賀の弁護士による離婚相談
…離婚に関する相談サイト。

滋賀の弁護士の交通事故無料相談
…交通事故相談サイト。

個人事業・会社の破産・倒産無料相談
…会社の破産相談サイト。
子連れ別居を阻止できるか?
2020年01月09日
突然ですが、今年からはこのブログは、原則として月・木曜日に記事を投稿しようと思います。
当初数年にわたって、平日毎日更新していましたが、2年くらい前から、業務の忙しさにかまけて、サボる日が出てきてしまいました。日を決めて置かないと、結局「今日も忙しい」で投稿を後回しにしてしまうので、今年はひとまず「月・木曜は必ず投稿!」というマイルールのもとにやっていこうと思います。
さて、離婚に関する法律相談で、「妻が子どもを連れて家を出て行きそう。どうやったら阻止できるか?」というような話はよくあります。
実際に、そのようなことを危惧しているとき、法的手段で別居を阻止することはできるのでしょうか?

確かに、民法には、夫婦同居義務が規定されています。
(民法第752条)
夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
しかしながら、同居を法的に強制的に実施させることができるわけではなく、実際問題として、離婚前に別居するというのは非常によくあることです。そして、どちらかといえば、妻が子を連れて家を出て行くという形が多いです。
法的に同居を強制的に実現する手段がない以上、別居を強制的に止めさせる方法も存在しません。
予防策としては、「子どもを勝手に連れての別居は承諾しない」というLINEなどを残しておくことや、事後策としては連れ去られた時点で速やかに家庭裁判所に子の引き渡しの仮処分と子の監護者指定の仮処分を申し立てるという方法があります。
しかしながら、それまで主として妻が子を監護してきたような場合には、上記のような事後策をとったとしても、子の監護者は妻が相当であるとして、夫からの子の引き渡しの申立ては認められない可能性が高いです。
したがって、弁護士としては、冒頭に記載したような、「妻が子どもを連れて出て行きそう」ということで相談をされても、なかなか効果的なアドバイスが見当たらず、非常に難しいところなんですよね。
結局のところ、そのような状況にならないのが一番で、また、いざ離婚となったときに親権を取りたいのであれば、その前から子どもの監護を配偶者以上に自分で行うことが必要ということになるのでしょうね
【滋賀県草津市の弁護士への相談はこちら】

滋賀の弁護士/草津駅前法律事務所
…このブログの筆者の事務所のメインサイト。

滋賀の弁護士による離婚相談
…離婚に関する相談サイト。

滋賀の弁護士の交通事故無料相談
…交通事故相談サイト。

個人事業・会社の破産・倒産無料相談
…会社の破産相談サイト。
当初数年にわたって、平日毎日更新していましたが、2年くらい前から、業務の忙しさにかまけて、サボる日が出てきてしまいました。日を決めて置かないと、結局「今日も忙しい」で投稿を後回しにしてしまうので、今年はひとまず「月・木曜は必ず投稿!」というマイルールのもとにやっていこうと思います。
さて、離婚に関する法律相談で、「妻が子どもを連れて家を出て行きそう。どうやったら阻止できるか?」というような話はよくあります。
実際に、そのようなことを危惧しているとき、法的手段で別居を阻止することはできるのでしょうか?

確かに、民法には、夫婦同居義務が規定されています。
(民法第752条)
夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
しかしながら、同居を法的に強制的に実施させることができるわけではなく、実際問題として、離婚前に別居するというのは非常によくあることです。そして、どちらかといえば、妻が子を連れて家を出て行くという形が多いです。
法的に同居を強制的に実現する手段がない以上、別居を強制的に止めさせる方法も存在しません。
予防策としては、「子どもを勝手に連れての別居は承諾しない」というLINEなどを残しておくことや、事後策としては連れ去られた時点で速やかに家庭裁判所に子の引き渡しの仮処分と子の監護者指定の仮処分を申し立てるという方法があります。
しかしながら、それまで主として妻が子を監護してきたような場合には、上記のような事後策をとったとしても、子の監護者は妻が相当であるとして、夫からの子の引き渡しの申立ては認められない可能性が高いです。
したがって、弁護士としては、冒頭に記載したような、「妻が子どもを連れて出て行きそう」ということで相談をされても、なかなか効果的なアドバイスが見当たらず、非常に難しいところなんですよね。
結局のところ、そのような状況にならないのが一番で、また、いざ離婚となったときに親権を取りたいのであれば、その前から子どもの監護を配偶者以上に自分で行うことが必要ということになるのでしょうね

【滋賀県草津市の弁護士への相談はこちら】

滋賀の弁護士/草津駅前法律事務所
…このブログの筆者の事務所のメインサイト。

滋賀の弁護士による離婚相談
…離婚に関する相談サイト。

滋賀の弁護士の交通事故無料相談
…交通事故相談サイト。

個人事業・会社の破産・倒産無料相談
…会社の破産相談サイト。
養育費算定表の改定版の発表
2019年12月23日
本日、裁判所が、養育費算定の際の基準となる「養育費算定表」の改定版を裁判所WEBサイトにて公表しました(http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou/)
公表内容は養育費の実務にどのような影響を与えるのでしょうか?

まず、今回の改定の重要なポイントの1つ目ですが、時事通信の報道によれば、『司法研修所は「改定版の公表そのものは、既に決まっている養育費を変更すべき事情には当たらない」としている。』という点です。
養育費については、一度当事者間で決めた場合でも、「特段の事情」があれば、養育費の増額や減額を家庭裁判所に求めることができます。
養育費の基準である養育費算定表が変更されることが「特段の事情」にあたるとすれば、今後養育費の増額を求める相談や調停が殺到する可能性があると思われましたが、裁判所が「養育費を変更すべき事情には当たらない」と言っているとのことで、そのような事態にはならないようです。
次に、変更後の金額や算定式ですが、算定式や考え方自体は大きく修正せず、また、金額についても従来の1.5倍くらいになるという噂もありましたが、比較的小規模な増額に留まるようです。
これは、裁判所が大きな変更による混乱を避けたのではないかとも推測されます。
いずれにしても、今日以降は、家庭裁判所でも新算定表が用いられ、現在調停や審判となっている案件についても適用されると考えられます。
まだネット上には旧算定表がアップされていたりしますから、十分に気をつけないといけませんね。
(筆者の事務所も、WEBサイトの確認・修正作業をしなければ… )
)
【滋賀県草津市の弁護士への相談はこちら】

滋賀の弁護士/草津駅前法律事務所
…このブログの筆者の事務所のメインサイト。

滋賀の弁護士による離婚相談
…離婚に関する相談サイト。

滋賀の弁護士の交通事故無料相談
…交通事故相談サイト。

個人事業・会社の破産・倒産無料相談
…会社の破産相談サイト。
公表内容は養育費の実務にどのような影響を与えるのでしょうか?

まず、今回の改定の重要なポイントの1つ目ですが、時事通信の報道によれば、『司法研修所は「改定版の公表そのものは、既に決まっている養育費を変更すべき事情には当たらない」としている。』という点です。
養育費については、一度当事者間で決めた場合でも、「特段の事情」があれば、養育費の増額や減額を家庭裁判所に求めることができます。
養育費の基準である養育費算定表が変更されることが「特段の事情」にあたるとすれば、今後養育費の増額を求める相談や調停が殺到する可能性があると思われましたが、裁判所が「養育費を変更すべき事情には当たらない」と言っているとのことで、そのような事態にはならないようです。
次に、変更後の金額や算定式ですが、算定式や考え方自体は大きく修正せず、また、金額についても従来の1.5倍くらいになるという噂もありましたが、比較的小規模な増額に留まるようです。
これは、裁判所が大きな変更による混乱を避けたのではないかとも推測されます。
いずれにしても、今日以降は、家庭裁判所でも新算定表が用いられ、現在調停や審判となっている案件についても適用されると考えられます。
まだネット上には旧算定表がアップされていたりしますから、十分に気をつけないといけませんね。
(筆者の事務所も、WEBサイトの確認・修正作業をしなければ…
 )
)【滋賀県草津市の弁護士への相談はこちら】

滋賀の弁護士/草津駅前法律事務所
…このブログの筆者の事務所のメインサイト。

滋賀の弁護士による離婚相談
…離婚に関する相談サイト。

滋賀の弁護士の交通事故無料相談
…交通事故相談サイト。

個人事業・会社の破産・倒産無料相談
…会社の破産相談サイト。
タグ :養育費
養育費算定表の改定と事件への影響
2019年12月19日
今月23日に、裁判所が養育費算定に用いる「養育費算定表」の改定版が発表されるということで、離婚事件をよく扱う弁護士は非常に注目しています。
本来、法律が改正されても、現在進行形で扱っている事件には影響しないことが多いのですが、今回の養育費算定表の改定は現在進行中の事件にも影響があるって知っていますか?

弁護士が交渉や裁判で扱っている事件は、「過去の出来事」に関するものがほとんどです。
たとえば交通事故ですと、事故が起こったのは過去のことですし、相続問題ですと、相続は死亡時に発生するとされていますから、過去(死亡時)に既に発生している相続関係について、どのように分割するかということを弁護士は取り扱うわけです。
そして、法律が改正されても、基本的には遡求効(遡っての適用)はありませんので、弁護をしている途中で法律が改正されたからといって、事件の方針が変わるとか、結論が変わるということはほとんどないんです。
ところが、今回予定されている養育費算定表の改定は、おそらく現在進行形の事件にも方針や結論に影響があります。
なぜかというと、養育費は基本的に、過去の権利の精算と言うよりはむしろ、将来のことを決めるからなんです。
離婚をするにあたって養育費をいくらにするかというのは、「離婚が成立した時点から、子どもが(原則)未成年でなくなるまで」の養育費をいくらにするかという、将来の話なんですよね。したがって、養育費算定表が改定されれば、今協議や調停をしている、将来の養育費の話に関して、直接の影響を受けることになると考えられます。
筆者も、離婚をよく扱う弁護士の一人なので、手帳にも「養育費算定表改訂日」と大きく記載してしまうほど重大な関心事なんですよね
【滋賀県草津市の弁護士への相談はこちら】

滋賀の弁護士/草津駅前法律事務所
…このブログの筆者の事務所のメインサイト。

滋賀の弁護士による離婚相談
…離婚に関する相談サイト。

滋賀の弁護士の交通事故無料相談
…交通事故相談サイト。

個人事業・会社の破産・倒産無料相談
…会社の破産相談サイト。
本来、法律が改正されても、現在進行形で扱っている事件には影響しないことが多いのですが、今回の養育費算定表の改定は現在進行中の事件にも影響があるって知っていますか?

弁護士が交渉や裁判で扱っている事件は、「過去の出来事」に関するものがほとんどです。
たとえば交通事故ですと、事故が起こったのは過去のことですし、相続問題ですと、相続は死亡時に発生するとされていますから、過去(死亡時)に既に発生している相続関係について、どのように分割するかということを弁護士は取り扱うわけです。
そして、法律が改正されても、基本的には遡求効(遡っての適用)はありませんので、弁護をしている途中で法律が改正されたからといって、事件の方針が変わるとか、結論が変わるということはほとんどないんです。
ところが、今回予定されている養育費算定表の改定は、おそらく現在進行形の事件にも方針や結論に影響があります。
なぜかというと、養育費は基本的に、過去の権利の精算と言うよりはむしろ、将来のことを決めるからなんです。
離婚をするにあたって養育費をいくらにするかというのは、「離婚が成立した時点から、子どもが(原則)未成年でなくなるまで」の養育費をいくらにするかという、将来の話なんですよね。したがって、養育費算定表が改定されれば、今協議や調停をしている、将来の養育費の話に関して、直接の影響を受けることになると考えられます。
筆者も、離婚をよく扱う弁護士の一人なので、手帳にも「養育費算定表改訂日」と大きく記載してしまうほど重大な関心事なんですよね

【滋賀県草津市の弁護士への相談はこちら】

滋賀の弁護士/草津駅前法律事務所
…このブログの筆者の事務所のメインサイト。

滋賀の弁護士による離婚相談
…離婚に関する相談サイト。

滋賀の弁護士の交通事故無料相談
…交通事故相談サイト。

個人事業・会社の破産・倒産無料相談
…会社の破産相談サイト。
法律改正でゴネ得は許されなくなる?
2019年05月16日
民事裁判で勝訴判決が出ても、実は相手が判決に従わない場合には、せっかく勝ったのに相手からお金が支払われず、判決がただの紙切れになってしまう場合があるんです。
でも、法律改正で、少しずつ「ゴネ得」を許さない制度になりつつあるって知っていますか?

勝訴判決が出ても相手が判決にしたがって金銭の支払いをしない場合、勝った側(債権者)は負けた側(債務者)の財産の強制執行=差押えの申立てを裁判所にすることができます。
代表的なのは給料の差押えと預金口座の差押えですね。
ところが、給料の差押えの場合、債務者の勤務先がどこなのかわからなければ差押えの申立てができません。また、預金口座の差押えの場合、どこの銀行のどこの支店に債務者の預金口座があるということを明示しなければ差押えの申立てができません。
そのため、どこで働いているかわからない、預金がどこにあるかわからない、ということで、せっかく裁判に勝訴したのに債権者が泣き寝入りをしてしまうケースが少なくないんですよね。
ところが、このたび民事執行法が改正され、銀行の本店に対して、「どこの支店に債務者の口座があるか」を裁判所から確認してもらったり、市役所や年金事務所に対して、「債務者はどこで勤務しているか」を裁判所から確認してもらったりする制度が創設されることとなりました。施行はまだですが、泣き寝入りしている被害者・権利者の救済につながると思うと、弁護士としてはちょっと期待してしまいます。
でも、判決が出ても支払わない人って、自営などで給料をもらっているわけではない人や、預金口座があってもその銀行から借り入れがある(※この場合は銀行の相殺が優先されるので差押えで回収できない)というケースが多く、法律が改正されても、意外と救済できるケースは少ないのかな…とも思ってしまいます
【滋賀県草津市の弁護士への相談はこちら】

滋賀の弁護士/草津駅前法律事務所
…このブログの筆者の事務所のメインサイト。

滋賀の弁護士による離婚相談
…離婚に関する相談サイト。

滋賀の弁護士の交通事故無料相談
…交通事故相談サイト。

個人事業・会社の破産・倒産無料相談
…会社の破産相談サイト。
でも、法律改正で、少しずつ「ゴネ得」を許さない制度になりつつあるって知っていますか?

勝訴判決が出ても相手が判決にしたがって金銭の支払いをしない場合、勝った側(債権者)は負けた側(債務者)の財産の強制執行=差押えの申立てを裁判所にすることができます。
代表的なのは給料の差押えと預金口座の差押えですね。
ところが、給料の差押えの場合、債務者の勤務先がどこなのかわからなければ差押えの申立てができません。また、預金口座の差押えの場合、どこの銀行のどこの支店に債務者の預金口座があるということを明示しなければ差押えの申立てができません。
そのため、どこで働いているかわからない、預金がどこにあるかわからない、ということで、せっかく裁判に勝訴したのに債権者が泣き寝入りをしてしまうケースが少なくないんですよね。
ところが、このたび民事執行法が改正され、銀行の本店に対して、「どこの支店に債務者の口座があるか」を裁判所から確認してもらったり、市役所や年金事務所に対して、「債務者はどこで勤務しているか」を裁判所から確認してもらったりする制度が創設されることとなりました。施行はまだですが、泣き寝入りしている被害者・権利者の救済につながると思うと、弁護士としてはちょっと期待してしまいます。
でも、判決が出ても支払わない人って、自営などで給料をもらっているわけではない人や、預金口座があってもその銀行から借り入れがある(※この場合は銀行の相殺が優先されるので差押えで回収できない)というケースが多く、法律が改正されても、意外と救済できるケースは少ないのかな…とも思ってしまいます

【滋賀県草津市の弁護士への相談はこちら】

滋賀の弁護士/草津駅前法律事務所
…このブログの筆者の事務所のメインサイト。

滋賀の弁護士による離婚相談
…離婚に関する相談サイト。

滋賀の弁護士の交通事故無料相談
…交通事故相談サイト。

個人事業・会社の破産・倒産無料相談
…会社の破産相談サイト。
スポーツ中の事故と法律
2018年05月23日
アメフトの試合で、相手の選手に怪我を負わした件がニュースになっていますね。
今回の件は、事故というよりも故意に怪我を負わしているようなので特殊なケースですが、スポーツ中に相手の選手を怪我させてしまうことはたまに起こりえます。
このような時に、怪我をさせた側が賠償責任を負うのかどうかって、実は難しい論点がたくさんある法律問題だって知っていますか?

本来、こちらのミスで相手に怪我をさせた場合には、過失傷害罪(刑法209条1項)が成立し、30万円以下の罰金または科料となります。
でも、スポーツでいつもこのような犯罪が成立していたら大変ですよね。野球のピッチャーはデッドボールを当てるたびに犯罪となりかねませんし、ボクシングなんて、そもそも相手を殴るわけですから、そのたびに暴行罪(刑法208条)が成立してしまいそうです。
これらのスポーツ中の行為に刑罰が科せられない理由としては、刑法35条の「正当行為」(=法令又は正当な業務による行為は罰しない)に該当するから、というのが一つの解釈です。ただ、ルール違反の行為の場合には、正当行為の範囲外、ということになるとも考えられます。
また、そもそも危険なスポーツについては、怪我を負うことがあることについて被害者の承諾があるから、それによって犯罪には該当しないのだ、という解釈もあります。
そして、刑事責任に問われないとしても、民事の損害賠償請求権は生じるのかどうか、などの問題もあるんですよね。
スポーツ事故に興味がある法学部の学生さんは、この分野の勉強を掘り下げてしてみたり、卒論のテーマにするのもよいかもしれませんね
【滋賀県草津市の弁護士への相談はこちら】

滋賀の弁護士/草津駅前法律事務所
…このブログの筆者の事務所のメインサイト。

滋賀の弁護士による離婚相談
…離婚に関する相談サイト。

滋賀の弁護士の交通事故無料相談
…交通事故相談サイト。

個人事業・会社の破産・倒産無料相談
…会社の破産相談サイト。
今回の件は、事故というよりも故意に怪我を負わしているようなので特殊なケースですが、スポーツ中に相手の選手を怪我させてしまうことはたまに起こりえます。
このような時に、怪我をさせた側が賠償責任を負うのかどうかって、実は難しい論点がたくさんある法律問題だって知っていますか?

本来、こちらのミスで相手に怪我をさせた場合には、過失傷害罪(刑法209条1項)が成立し、30万円以下の罰金または科料となります。
でも、スポーツでいつもこのような犯罪が成立していたら大変ですよね。野球のピッチャーはデッドボールを当てるたびに犯罪となりかねませんし、ボクシングなんて、そもそも相手を殴るわけですから、そのたびに暴行罪(刑法208条)が成立してしまいそうです。
これらのスポーツ中の行為に刑罰が科せられない理由としては、刑法35条の「正当行為」(=法令又は正当な業務による行為は罰しない)に該当するから、というのが一つの解釈です。ただ、ルール違反の行為の場合には、正当行為の範囲外、ということになるとも考えられます。
また、そもそも危険なスポーツについては、怪我を負うことがあることについて被害者の承諾があるから、それによって犯罪には該当しないのだ、という解釈もあります。
そして、刑事責任に問われないとしても、民事の損害賠償請求権は生じるのかどうか、などの問題もあるんですよね。
スポーツ事故に興味がある法学部の学生さんは、この分野の勉強を掘り下げてしてみたり、卒論のテーマにするのもよいかもしれませんね

【滋賀県草津市の弁護士への相談はこちら】

滋賀の弁護士/草津駅前法律事務所
…このブログの筆者の事務所のメインサイト。

滋賀の弁護士による離婚相談
…離婚に関する相談サイト。

滋賀の弁護士の交通事故無料相談
…交通事故相談サイト。

個人事業・会社の破産・倒産無料相談
…会社の破産相談サイト。
司法試験に短期合格するためには?
2018年05月18日
司法試験って、1回ですぐに合格する人もいれば、すごく勉強していて知識もあるのになかなか合格しない人もいます。
特に、筆者が受験した頃の旧司法試験の論文式試験はその傾向が高かったです。
すぐに合格する人と、なかなか合格しない人の違いっていったい何なんでしょうか?
司法試験の論文の問題って、「何条には何と書いてありますか?」というような知識だけを問う問題ではないんです。
実際の法律トラブルの事例などが問題となっていて、それに対する解決方法を論文で書かせるんですね。
そのような問題の解き方って、事例を見て、自分の頭の中にある知識の引出しから、適切な材料(条文や判例知識等)を持ち出して、それを組み合わせて回答を出す、というような作業なんです。
まだ勉強して年数が浅いと、知識の引出しの数が少なく、重要な条文・判例しか引出しには入っていません。そうすると、事例問題を見たときに、引出しの数が少ないからこそ、その中で最も適切な材料を持ち出すのが容易なんです。
他方で、勉強して年数が経ち、どんどん情報量が増えていくと、知識の引出しの数がどんどん増えていき、重要な条文・判例のみならず、マニアックな判例などの知識もあふれてきます。そうすると、いざ事例問題を見たときに、引出しの数が多すぎて、本当に必要な材料を持ち出して回答することが難しくなってくるんですよね。
ですので、不合格になったときに、「まだ勉強(知識)が足りないから落ちたんだ。もっと勉強しよう。」と知識(引出し)を増やす方向の努力をすると、合格がますます遠のいてしまう、ということがよくあるんです。むしろ、細かい知識をそぎ落として、重要な判例・条文のみをしっかりと理解する方が、短期合格への近道なんですよね。
なんて話を、かつて司法試験に合格してから司法修習までの間に、予備校にかつがれて?、全国各地で講演していました。今日の記事を書いていて、久しぶりにその頃のことを思い出してしまいました
【滋賀県草津市の弁護士への相談はこちら】

滋賀の弁護士/草津駅前法律事務所
…このブログの筆者の事務所のメインサイト。

滋賀の弁護士による離婚相談
…離婚に関する相談サイト。

滋賀の弁護士の交通事故無料相談
…交通事故相談サイト。

個人事業・会社の破産・倒産無料相談
…会社の破産相談サイト。
特に、筆者が受験した頃の旧司法試験の論文式試験はその傾向が高かったです。
すぐに合格する人と、なかなか合格しない人の違いっていったい何なんでしょうか?
司法試験の論文の問題って、「何条には何と書いてありますか?」というような知識だけを問う問題ではないんです。
実際の法律トラブルの事例などが問題となっていて、それに対する解決方法を論文で書かせるんですね。
そのような問題の解き方って、事例を見て、自分の頭の中にある知識の引出しから、適切な材料(条文や判例知識等)を持ち出して、それを組み合わせて回答を出す、というような作業なんです。
まだ勉強して年数が浅いと、知識の引出しの数が少なく、重要な条文・判例しか引出しには入っていません。そうすると、事例問題を見たときに、引出しの数が少ないからこそ、その中で最も適切な材料を持ち出すのが容易なんです。
他方で、勉強して年数が経ち、どんどん情報量が増えていくと、知識の引出しの数がどんどん増えていき、重要な条文・判例のみならず、マニアックな判例などの知識もあふれてきます。そうすると、いざ事例問題を見たときに、引出しの数が多すぎて、本当に必要な材料を持ち出して回答することが難しくなってくるんですよね。
ですので、不合格になったときに、「まだ勉強(知識)が足りないから落ちたんだ。もっと勉強しよう。」と知識(引出し)を増やす方向の努力をすると、合格がますます遠のいてしまう、ということがよくあるんです。むしろ、細かい知識をそぎ落として、重要な判例・条文のみをしっかりと理解する方が、短期合格への近道なんですよね。
なんて話を、かつて司法試験に合格してから司法修習までの間に、予備校にかつがれて?、全国各地で講演していました。今日の記事を書いていて、久しぶりにその頃のことを思い出してしまいました

【滋賀県草津市の弁護士への相談はこちら】

滋賀の弁護士/草津駅前法律事務所
…このブログの筆者の事務所のメインサイト。

滋賀の弁護士による離婚相談
…離婚に関する相談サイト。

滋賀の弁護士の交通事故無料相談
…交通事故相談サイト。

個人事業・会社の破産・倒産無料相談
…会社の破産相談サイト。
タグ :司法試験
養育費が大きく変わる?
2018年05月09日
離婚後の養育費や、離婚前の生活費(婚姻費用)を裁判所が決める場合、裁判所が作成した「養育費算定表」という表に基づいて決まることがほとんどです。
ところが、この養育費算定表の妥当性や見直しに向けて、司法研修所(最高裁判所の研究・研修機関)が検討を開始するようです。
もし養育費算定表が改定されれば、離婚をよく扱う弁護士にとっては、非常に大きな影響があるってご存じですか?

もし改定をするとしたら、基本的には、養育費や生活費の金額を増額させる方向での改定だと思われます。
妻側の弁護も、夫側の弁護も担当する弁護士からすれば、現在の算定表でも、養育費をもらう側(=たいていは妻)からすれば「こんな少ない額ではやっていけない」という声がほとんどであり、他方で、養育費を払う側(=たいていは夫)からすれば「こんなに払っていては自分が生活できない」という声がほとんどです。
養育費が増額の方向で改定されれば、夫側の不満がさらに増えるでしょうね。
夫側の不満が高まりやすいのは、住宅ローンを抱えているケースです。
よくある相談としては、「妻の要望で、一戸建ての家を無理して建てたのに、建てた途端妻が離婚を切り出してきた」というものです。
養育費算定表では、双方の収入をベースに養育費を決めるため、住宅ローンなどの支出は基本的に考慮しません。家族が住むために無理して購入した一戸建てのため、住宅ローンの負担が大きく、さらに養育費を払うと生活ができない、という相談はかなり多いです。
一人で住むには家が大きすぎるので、売ろうと思っても、オーバーローンだと「追い金」(=売却額とローン残額の差額)を払わないと売ることも原則としてできません。そのため、不必要な大きい家に住み続け、住宅ローンと養育費を払わなければならない、という状況になるんですね。
養育費算定表が改定され、養育費が増額されると、そのような相談がますます増えそうです。他方で、妻側からは、「算定表が変わったから養育費増額請求がしたい」という相談も増えそうです。
司法研修所がどういう検討結果を出すのか、離婚をよく扱う弁護士の1人として、興味津々なところです
【滋賀県草津市の弁護士への相談はこちら】

滋賀の弁護士/草津駅前法律事務所
…このブログの筆者の事務所のメインサイト。

滋賀の弁護士による離婚相談
…離婚に関する相談サイト。

滋賀の弁護士の交通事故無料相談
…交通事故相談サイト。

個人事業・会社の破産・倒産無料相談
…会社の破産相談サイト。
ところが、この養育費算定表の妥当性や見直しに向けて、司法研修所(最高裁判所の研究・研修機関)が検討を開始するようです。
もし養育費算定表が改定されれば、離婚をよく扱う弁護士にとっては、非常に大きな影響があるってご存じですか?

もし改定をするとしたら、基本的には、養育費や生活費の金額を増額させる方向での改定だと思われます。
妻側の弁護も、夫側の弁護も担当する弁護士からすれば、現在の算定表でも、養育費をもらう側(=たいていは妻)からすれば「こんな少ない額ではやっていけない」という声がほとんどであり、他方で、養育費を払う側(=たいていは夫)からすれば「こんなに払っていては自分が生活できない」という声がほとんどです。
養育費が増額の方向で改定されれば、夫側の不満がさらに増えるでしょうね。
夫側の不満が高まりやすいのは、住宅ローンを抱えているケースです。
よくある相談としては、「妻の要望で、一戸建ての家を無理して建てたのに、建てた途端妻が離婚を切り出してきた」というものです。
養育費算定表では、双方の収入をベースに養育費を決めるため、住宅ローンなどの支出は基本的に考慮しません。家族が住むために無理して購入した一戸建てのため、住宅ローンの負担が大きく、さらに養育費を払うと生活ができない、という相談はかなり多いです。
一人で住むには家が大きすぎるので、売ろうと思っても、オーバーローンだと「追い金」(=売却額とローン残額の差額)を払わないと売ることも原則としてできません。そのため、不必要な大きい家に住み続け、住宅ローンと養育費を払わなければならない、という状況になるんですね。
養育費算定表が改定され、養育費が増額されると、そのような相談がますます増えそうです。他方で、妻側からは、「算定表が変わったから養育費増額請求がしたい」という相談も増えそうです。
司法研修所がどういう検討結果を出すのか、離婚をよく扱う弁護士の1人として、興味津々なところです

【滋賀県草津市の弁護士への相談はこちら】

滋賀の弁護士/草津駅前法律事務所
…このブログの筆者の事務所のメインサイト。

滋賀の弁護士による離婚相談
…離婚に関する相談サイト。

滋賀の弁護士の交通事故無料相談
…交通事故相談サイト。

個人事業・会社の破産・倒産無料相談
…会社の破産相談サイト。
タグ :養育費
「平成35年」という表記で問題はないの?
2018年01月09日
新年あけましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いします。
さて、今年は平成30年ですが、おそらく来年には改元されると想定されています。契約書などに、「平成35年」と書かれているのに、平成が改元された場合、契約書の効力に問題は生じないのでしょうか?

結論から言えば、「平成35年」と書いていれば、2023年のことだというのは容易にわかりますから、契約書の効力に問題は生じません。
実際に、裁判所が作成する和解条項では、西暦ではなく元号を用いるので、今でも長期分割払いの和解をするときに、「平成35年」と言った表記で文書を作成することが普通にあります。
でも、いくら効力に問題がないといっても、平成35年という元号がほぼ無いのであれば、そこはわかりやすいように西暦表示をした方がいい気がするんですけどね
【滋賀県草津市の弁護士への相談はこちら】

滋賀の弁護士/草津駅前法律事務所
…このブログの筆者の事務所のメインサイト。

滋賀の弁護士による離婚相談
…離婚に関する相談サイト。

滋賀の弁護士の交通事故無料相談
…交通事故相談サイト。

個人事業・会社の破産・倒産無料相談
…会社の破産相談サイト。
さて、今年は平成30年ですが、おそらく来年には改元されると想定されています。契約書などに、「平成35年」と書かれているのに、平成が改元された場合、契約書の効力に問題は生じないのでしょうか?

結論から言えば、「平成35年」と書いていれば、2023年のことだというのは容易にわかりますから、契約書の効力に問題は生じません。
実際に、裁判所が作成する和解条項では、西暦ではなく元号を用いるので、今でも長期分割払いの和解をするときに、「平成35年」と言った表記で文書を作成することが普通にあります。
でも、いくら効力に問題がないといっても、平成35年という元号がほぼ無いのであれば、そこはわかりやすいように西暦表示をした方がいい気がするんですけどね

【滋賀県草津市の弁護士への相談はこちら】

滋賀の弁護士/草津駅前法律事務所
…このブログの筆者の事務所のメインサイト。

滋賀の弁護士による離婚相談
…離婚に関する相談サイト。

滋賀の弁護士の交通事故無料相談
…交通事故相談サイト。

個人事業・会社の破産・倒産無料相談
…会社の破産相談サイト。