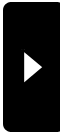弁護士・裁判官・検察官のどれがいい?
2012年11月12日
司法試験に合格すると,司法修習生といって,約1年間,裁判所・検察庁・弁護士会で研修を積む期間があります。その間に,弁護士になるか,裁判官になるか,検察官になるか,それぞれ進路を決めることになります。
さて,それぞれのうち,いったいどの職業がいいのでしょうか? 筆者の独断ですが,それぞれの印象をみてみましょう。
①裁判官
・公務員なので安定している。
・研修制度などもしっかりしている。
・お金のことを考えなくていい。事件処理だけに集中できる。
・基本的には,法廷と裁判官室と準備手続室という裁判所内を行ったり来たり。
・机に向かって起案をしている時間が他の職業より多い。
・当事者と1対1で面と向かって話をすることはほとんどない。
・全国転勤がある。
→弁護士や検察官に比べると,最も知的作業が多いといえますね。また,既に弁護士や検察官が事件として形を作り上げてきたものを,法廷で判断しますので,弁護士や検察官に比べれば,泥臭い面は少ないと言えそうです。また,公務員の安定感や育休の取りやすさなどから,近年では女性の志望者が増えているようです。
②検察官
・公務員なので安定している。
・ずっと刑事事件のみを扱う。
・体育会気質があると言われている(特に昔は)
・全国転勤だが,何年か経つと,東日本か西日本かが決まってくると言われている。
・基本的には,取り調べ室(執務室)と裁判所の往復。
・研修制度などはしっかりしている。
→実は,検察官の仕事や検察庁の気質は,結構謎だったりします。秘密を扱うので当然ではあるのですが,ブログなどをやっている人がほとんどいないんですよね。
裁判官や弁護士と異なり,ずっと刑事事件の訴える側という一方的立場で仕事をしますから,正義感なども必要でしょう。なお,厳格な決裁制度があり,ピラミッド構造の組織を持つのも特色です。
③弁護士
・自営業なので,不安定。収入に大きな差がある。
・民事も刑事も,法廷事件も法廷外も扱うので,非常に幅が広い。
・特に町弁(町医者的弁護士)の場合,ほとんどが零細事業主なので,研修が制度としては整っていないことが多い。
・当事者と1対1になる場面も多いが,公務員ではないので,組織的に保護されているわけではない。
・独立後は,自分で賃料を払い,事務員を雇って行かなくてはならない。
・自営業なので,自分自身で休みや仕事のペースを決めやすい。(逆に,決断力がなければ休みが取れない)
→弁護士の最も特徴的な点は,裁判官・検察官と異なり,自営業という点でしょう。いくら弁護士の仕事に興味を持っていても,自営業という点がネックになる人は少なくないかもしれません。
また,裁判は扱わずに海外企業との交渉を扱う弁護士や,民事事件のみを扱う弁護士など,様々な種類の弁護士がいます。
というわけで,一概に,どれがよくてどれが悪いとは言えないのではないかと思います。
これから司法修習が始まるみなさんも,イメージだけで決めてしまうのではなく,しっかりと修習中にそれぞれの職業を実際に目で見て,後悔のない決断をして欲しいですね
滋賀県草津市の弁護士への相談はこちら

↑当事務所の総合サイト。

↑当事務所の交通事故専門HP。

↑当事務所の個人事業・会社破産専門HP。
さて,それぞれのうち,いったいどの職業がいいのでしょうか? 筆者の独断ですが,それぞれの印象をみてみましょう。
①裁判官
・公務員なので安定している。
・研修制度などもしっかりしている。
・お金のことを考えなくていい。事件処理だけに集中できる。
・基本的には,法廷と裁判官室と準備手続室という裁判所内を行ったり来たり。
・机に向かって起案をしている時間が他の職業より多い。
・当事者と1対1で面と向かって話をすることはほとんどない。
・全国転勤がある。
→弁護士や検察官に比べると,最も知的作業が多いといえますね。また,既に弁護士や検察官が事件として形を作り上げてきたものを,法廷で判断しますので,弁護士や検察官に比べれば,泥臭い面は少ないと言えそうです。また,公務員の安定感や育休の取りやすさなどから,近年では女性の志望者が増えているようです。
②検察官
・公務員なので安定している。
・ずっと刑事事件のみを扱う。
・体育会気質があると言われている(特に昔は)
・全国転勤だが,何年か経つと,東日本か西日本かが決まってくると言われている。
・基本的には,取り調べ室(執務室)と裁判所の往復。
・研修制度などはしっかりしている。
→実は,検察官の仕事や検察庁の気質は,結構謎だったりします。秘密を扱うので当然ではあるのですが,ブログなどをやっている人がほとんどいないんですよね。
裁判官や弁護士と異なり,ずっと刑事事件の訴える側という一方的立場で仕事をしますから,正義感なども必要でしょう。なお,厳格な決裁制度があり,ピラミッド構造の組織を持つのも特色です。
③弁護士
・自営業なので,不安定。収入に大きな差がある。
・民事も刑事も,法廷事件も法廷外も扱うので,非常に幅が広い。
・特に町弁(町医者的弁護士)の場合,ほとんどが零細事業主なので,研修が制度としては整っていないことが多い。
・当事者と1対1になる場面も多いが,公務員ではないので,組織的に保護されているわけではない。
・独立後は,自分で賃料を払い,事務員を雇って行かなくてはならない。
・自営業なので,自分自身で休みや仕事のペースを決めやすい。(逆に,決断力がなければ休みが取れない)
→弁護士の最も特徴的な点は,裁判官・検察官と異なり,自営業という点でしょう。いくら弁護士の仕事に興味を持っていても,自営業という点がネックになる人は少なくないかもしれません。
また,裁判は扱わずに海外企業との交渉を扱う弁護士や,民事事件のみを扱う弁護士など,様々な種類の弁護士がいます。
というわけで,一概に,どれがよくてどれが悪いとは言えないのではないかと思います。
これから司法修習が始まるみなさんも,イメージだけで決めてしまうのではなく,しっかりと修習中にそれぞれの職業を実際に目で見て,後悔のない決断をして欲しいですね

滋賀県草津市の弁護士への相談はこちら

↑当事務所の総合サイト。

↑当事務所の交通事故専門HP。

↑当事務所の個人事業・会社破産専門HP。
弁護士会の活動の有償化orペナルティ化?
弁護士には夜型が多い? 朝型が多い?
弁護士ってなぜ同業者同士で飲みたがるの?
弁護士が当事者になるとたくさん裁判してくるの?
弁護士のデータ通信量と携帯キャリア
弁護士からみた不倫をする男性の特徴
弁護士には夜型が多い? 朝型が多い?
弁護士ってなぜ同業者同士で飲みたがるの?
弁護士が当事者になるとたくさん裁判してくるの?
弁護士のデータ通信量と携帯キャリア
弁護士からみた不倫をする男性の特徴
Posted by
弁護士 中井陽一
at
08:08
│
弁護士雑談